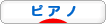注:緑色の文字は引用部分(数字はページ番号)、赤い文字は私が強調したもの
■自分の音を聴く能力の重要性
演奏しながら自分の音を聴くことの重要性が語られる。そして、「録音」の利用により、「聴くこと」の習慣や能力が育ちにくくなっていることを危惧している。
34
多くのピアニストが自分の演奏を聴くために録音しはじめた。わたしとしてはこの習慣は最悪に思える。ほんとうは演奏しているその瞬間になにが起きているか意識する態度を育てるべき…
技術的なことにいっさい煩わされることなく指が音楽を奏でる状態になってはじめて、ゆとりをもって自分の音を聴き、新しい音色効果や、より巧みなルバートを試しながら解釈を導くことができる。
36
…ピアノの練習は往々にして頭を使わず、純粋に機械的なのだが…。もちろん、これと違う練習もある。それは知性だけでなく、自分の音を聴く能力の要求される練習、つまり和音のなかの声部のバランスをとり、メロディの輪郭を描き、音色と各音の重みを決める作業だ。
■ピアノを学ぶことは音楽史の発展をたどるようなもの
ピアノを学ぶことで音楽史をたどれる、というより、一通りの音楽史をたどれるだけの曲を勉強しなさい、と言っているように思える。「触覚から聴覚へ」という観点は新鮮で興味深い。
38~
音楽史は明確に触覚から聴覚へ移る…。
ビザンツ音楽、グレゴリオ聖歌のようなモノフォニー音楽
→指で線をなぞるように、時間軸のなかでたどることができそう…
13世紀:ポリフォニー音楽
→並行に走る複数のラインとして感じとれる
バロック音楽の対位法
→和音の垂直な構成音が時間軸のなかを動くとともに、通奏低音が各声部の水平なラインと交差する
ハイドン、モーツァルト
→この水平、垂直要素が融合する
シューマン、リスト
→声部が神秘的かつあいまいに溶け合ってラインが消えはじめる
ワグナー~リヒャルト・シュトラウス
→この溶解傾向はワグナーに引き継がれ、彼がしだいに半音階法を多用するようになって和音の定義があいまいになり、リヒャルト・シュトラウスでほとんど極限にまで達する
ドビュッシー以降
→ドビュッシーが小節ごとにはっきりと区切られるリズム感覚を打ち壊し、垂直の和音構造はシェーンベルクとその弟子たち(いわゆる新ウィーン楽派)によって骨抜きにされた(ただし新古典派のストラヴィンスキーは和声言語の完全性を壊してしまった。)
最後に、あたかも指で地図上をたどるような触覚の証明とも言える、形式をめぐるさまざまな基本要素 ― モチーフ、ゼクエンツの反復、規則正しい画一的な拍子など ― が、ブーレーズとシュトックハウゼンによって取り除かれる。
■ピアノには三つの限界
ピアノの音の特性を、ピアノ以外の音楽を模倣する場合の「限界」にそって説明。音質の均一性に関しては、改めて認識させられた。「均一」な音質を目指しながら、ふだん何となく感じているように、低音・中音・高音のそれぞれの音域は明らかに音質が異なっている。それを音楽にどう活かすか、ということだと思う。
42
声楽曲やピアノ以外の楽器の曲を再現するとき、ピアノには三つの限界がある。全音域にわたって相対的に音質が均一なこと(最低音部と最高音部の音色がじつは非常に異なるのだが、理論としては通用している)、一度出した音を制御しにくいこと、調律したピアノは途中でピッチを変えられないこと、の三つである。
■音楽によって身体の使い方が変わる
著者の体験したエピソードが面白い。ドビュッシーばかり練習していたあとにベートーヴェンを弾いたら、初めのうちは指が動きにくくて困ったという話である。音楽が変わると弾き方、つまり身体や筋肉の使い方も変わる、ということだ。
56
…バッハを弾くときとバルトークを弾くときとでは、指の置き方からして違う。違う筋肉を使うからだ。レガートのタッチはベートーヴェンとドビュッシーとでは違う…
『ピアノ・ノート』

【関連記事】
《「ピアノ・ノート」:紹介&目次》
《7分で読めるピアノの本(6):ピアノ・ノートとシーモアさん》
《ピアノの本》