1ヵ月近く前に、《現代ピアノ音楽の勉強を始める》という記事で、『線の音楽』という本をご紹介した。
「1979年、日本の現代音楽の作曲と聴取に革新をもたらした記念碑的名著、待望の復刊!」と紹介されており、期待して読み始めた。のだが、少し文章が難しくて、けっこう時間がかかってしまった。しかし、内容としては期待した以上に面白く読み応えのあるものであった。
『線の音楽』(近藤 譲 著、アルテスパブリッシング、2014)
なかなか中身が濃いので、「意訳」のような感じで、「自分が理解した」範囲の内容を書いてみようと思う。
■ 調性音楽の時代
まず、作曲という行為は2つの部分に分けて考えることができる。
「素材としての楽音を創り出す」+「楽音を使って音楽を組み立てる」
原文では、「音の分節」+「音の連接」となっている。私自身、作曲というのは後者の「音楽の組み立て」をイメージしていたのだが、どうもそうではないらしいのだ。その辺りを含めて、歴史を見てみる。
古典派・ロマン派などの「調性音楽」の時代、「楽音」といえば楽器の音と人の声にほぼ限られていた。なので、「音楽の組み立て」だけが作曲の作業であった。また、その組み立て方が和声法や対位法であり、ソナタ形式などの楽曲形式であった。
音楽を組み立てる方法は「構築的(階層的)」なものであり、それにはいくつかのルールのようなものがあった。「音→音階→和音→特定の中心音(核音)との関係による和音のグルーピング」「音→動機→フレーズ→楽段→楽節→楽章」や「旋律」「リズム」「形式」など、である。
■ 12音技法とトータル・セリー音楽
調性からの脱却を目指して、「12音技法」が登場する。これは、上記のルールの中の「音→音階→和音→…」という「音高」の体系を拒否するものである。それ以外のルールは依然として存在していた。組み立て方に「反行」フーガなどの古典的な技法が使われているのが面白い。
それが次の「トータル・セリー(総音列)音楽」になると、音高以外の音の要素、たとえば音の長さ・強さ・アタックなどの体系も拒否されることになる。12音技法で、12の音を平等に扱って配列するのと同じ考え方で音の長さなども扱う、ということになる。
これらの技法は、「作曲方法としては組織化されているが、聴覚上は何の組織化ももたらさない」。つまり、作曲家の意図したものが聴き手には聴こえない(伝わらない)、ということが起きてしまった。
ところが聴き手としては、音の連なりの中から何かを聴き取ろうとする。しかし、聞こえてくるのは「音楽」というより、音の群れがよく分からないやり方で連続している「現象」ということになってしまう。
■ クラスター(音群)音楽の登場
この、結果としての「音の群れ」を、逆に目的としたのが「クラスター音楽」と考えることができる。つまり、目的とする「音群」を得るために音を積み重ねるわけだ。
ここに来て、「素材としての楽音を創り出すこと」(音の分節)が、作曲家の新たな作業として登場することになる。テープ音楽(自然界の音を取り込む)、電子音楽(電子的に音を作り出す)などの流れとも相まって、音楽を構成する音の幅が一気に広がったのである。
しかし困ったことが起きた。この「音群」をつなぎ合わせて「音楽を組み立てる」ための方法論が見つからなかったのだ。結果的には、従来の組み立て方が使えるように「音群」を調整する(音高をそろえるなど)の方法がとられた。
■ プリペアド・ピアノと偶然性の音楽
ジョン・ケージが発明した「プリペアド・ピアノ」は、面白い性質を持っている。「楽音」(素材)としては非常に非統一である。しかし「鍵盤楽器」であることによって、音楽の組み立て方は、ある意味で従来の方法が使える。
一方で、困った問題もある。楽器によって、また「プリペア」の仕方の細かい違いにより、作曲家が意図した音を再現することが極めて困難であったのである。そのこともあって、ケージは「偶然性の音楽」(確率や偶然によってできた音を使う)へと向かう。
ところが、「偶然性」とは、いいかえると「作曲家が結果をコントロールしない」ということでもある。結果として鳴り響く音の連なりから何らかの「音楽」を聴き取るのは聴き手に託されることになる。
■ 作曲の役割分担の変化:聴き手の参画
従来、作曲という行為は作曲家がコントロールしていた。素材の楽音を作るのも、音楽として組み立てるのも作曲家であった。演奏家は作曲家の意図したものを再現するのが仕事であり、聴き手はそれをただ受動的に受け取り感じるのが役割?であった。
しかし、作曲家が新しいものを創り出す模索をしてきた結果、出てきたことは、作曲(音楽を形成すること)に関する「聴き手の参画」ということである。
つまり、作曲家は何らかの音の連なりを提示するだけ(作曲家によって100%コントロールされているとは限らない)。その音を聴いて、そこに「音楽」を聴き出すのは聴き手の作業、ということである。従って、聴き手によって、あるいは聴くたびに違う「音楽」が聞こえることもあり得る。
「素材としての楽音を創り出す」+「楽音を使って音楽を組み立てる」という作曲作業の中の、後半の一部が聴く側に移された、と言ってもよい。あるいは、調性音楽における「ルール(和声・楽曲形式など)→作曲→音」の流れが、極端に言えば「音→聴覚→ルール(構造・関係性など)」という流れに変わった、とも言えるかも知れない。
■ 「線の音楽」
で、近藤氏が提唱し実践する「線の音楽」である。(これがかなり難しくて、私の力量では簡単には説明できないのだが…)
まず「楽音を創り出す」部分を一旦棚上げすることで、「音楽を組み立てる」(連接)に注目するというアプローチである。ポイントは、聴き手に「音楽」(音の構造・関係性・グルーピングなど)を聴き取らせることにある。しかも、聴き取られる音の「関係性」が安定しないような工夫がされる。
音楽を聴くことが、提示される音の流れの中から、緊張感をもって「関係性」を追い続ける体験となる。近藤氏の言葉では次のようになる。
「漠然としたグルーピング『可能的』状態で提示されたものの内に、聴き手が自ら聴覚的グルーピングを見いだしていく。それを誘導する音楽、そのような聴き方に導く音楽が可能ではないか?」
これ以上は、実際の近藤氏の音楽をもっとたくさん聴いて、自分自身の感じ方をもとに深めるしかないと思っている。
■近藤譲氏の「夢」
以上は、この本の中の「アーティキュレイション」を「意訳」したものである。その最後に、近藤氏は次のような「夢」を語っている。
「この新しい音楽は、人を訪れる現実とその現実を捉える人の認識との、静かな潮汐運動のようなせめぎ合いである。現実の中で人が、経験知によって知覚できるものだけを『自然』と捉えるように、立ち現れてくる音の内に『音楽』を聴き出すこと。ここでの『現実』は仕組まれた音ではあるが、そこに『音楽』を見いだす耳は、『自然』を見いだす身体のように、人の心を深く安めることができるかも知れない…」
私の「意訳」:
人間が「自然っていいなぁ」と認識している「自然」は、実は現実の環境の中から人間の知覚が選び出したものである。おなじように、作曲家が提示した音(という環境)のなかから「この音楽っていいなぁ」と人間が自らの聴覚によって選び出す(聴き取る)ような音楽のあり方が可能ではないか。そして、それは人の心を深く安めることができるかもしれない、自然が人の心を安めるように…。
近藤氏が35年前に見た「夢」はどうなったのであろう?
【関連記事】
《現代ピアノ音楽の勉強を始める》
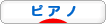

0 件のコメント:
コメントを投稿