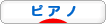第1部「アーティキュレイション」
アーティキュレイション 第 Ⅳ 章
『線の音楽』のはじまり
>「線の音楽」は、新しい響きの追求(新しい楽音の分節)を一時棚上げするところから始まった。ここで、問題は「分節」の方法論から離れ、再び「連接」の方法論へ移る。(12音音楽や総音列音楽とは異なった視点から)
>「既楽音」の崩壊を前提とし、また作曲方法上の方便的な書式技法としての組織ではない、「聴覚的」に認知され得る性質のものとして、構築性に代わるグルーピングの取り扱いについての方法がありうるか? あるとすれば、どのようなものであり、どのような音楽をもたらすのか?
最初の取り組み:『オリエント・オリエンテーション』
>1973年1月に作曲した『オリエント・オリエンテーション』は意識的にこの方向へ向かった最初の作品である。(ハーピスト、篠崎史子の依頼)
>これは、同種2楽器(アタック音の立ち上がりが明確な方がよい)のための曲である。テンポ、音の強さ、音色を一定とし、使う15個の音を選びランダムに並べた、「音高」のみをパラメータとした一本の旋律からなる。2つのパートはユニゾンになったり、わずかにアタックや音高がずれたりしながら進む。
>部分的な音の偏りにより、聴き手はそこに核音を感じることになる。この偶成的・聴覚的な核音は、聴く毎に、あるいは聴き手によって変わることになるはずだ。そして、「音→核音との関係によるグルーピング」が聴覚的に生じる。
>漠然としたグルーピング「可能的」状態で提示されたものの内に、聴き手が自ら聴覚的グルーピングを見いだしていく。それを誘導する音楽、そのような聴き方に導く音楽が可能ではないか?
>このような音楽では、聴き手の「グルーピングを聴き出す」仕事を持続した緊張状態の中に置くことができなかった場合には、この音楽の結果は芳しくないものとなる。
「関係」「予測」「持続」
>調性音楽では、グルーピングは音相互間に確立された「関係」として聴覚的に認識される。この関係は、次の音を予測することを可能にする。それにより、心理的に音がつながり音楽の持続が生まれる。〔(確立され認識された)「関係」→予測→持続〕という図式で表される。
>調性音楽では、「音から音へ」のレベルから「フレーズからフレーズへ」「楽節から楽節へ」というより高次のグルーピング段階に引き上げ、それを制御して、作品を明確な方向性をもった持続(目的的持続)に仕立て上げる。ここでは、この目的的持続を経験することが「音楽を聴く」ことであって、「関係」はそれを生み出すための方法論的な前提でしかない。
>しかし、ここで探ろうとしている音楽は、「関係」を聴き出すことをその体験の中心に据えようとしている。そのためには、図式を〔持続→(聴き出された)「関係」→予測(…→持続)〕と入れ換える必要がある。
〔持続→「関係」→予測〕による音楽
>何らかの方法で作られた持続から、潜在する「関係」が聴き出されれば、そこに予測が成り立ち、をの予測がさらに持続を導く。この持続は、予測の力を借りることなく他の方法で既に確立されている必要がある。
>聴き出された「関係」から生ずる予測の射程はきわめて短いため、それが直接に音楽の持続を作り出す大きな原動力とはなりえない。しかし、ここでの予測は新たな役割を担う。それは、「関係」を「聴き出していく」という行為に対する聴き手の興味を持続的なものにするということだ。
>聴き出された「関係」による予測は、次に現れる音によりゆらぐ。予測にそった音が現れれば安定し、そうでなければ、不安定なもの、あるいはすでに崩れ去るべきものと認識される。(※予測と現実のフィードバックにより、常に流動し、あるいは修正されていく)
>崩れ去るべき「関係」に会えば、聴き手は再び新たな「関係」を聴き出していかねばならない。聴き手は緊張した各瞬間の中でその「関係」を追う旅を続けることになる。偶然に現れる「関係」を受け容れるのではなく、心理的な予測が加わることで、聴き手は、予測と現実の摩擦のなかで、「関係」を駒にしたゲームを楽しむことになる。
>このようにして、「関係」の体験を第一義とする音楽が可能となるだろう。その音楽は、聴き手の予測を喚起し得るほどに秩序的であり、ある「関係」が聴き出されはするがそれが安定せず幻影のように移ろう状態を作り出すことが要請される。
>こうした構造を作り出すこと、そしてこの構造の前提となる持続を〔予測→持続〕に頼らずに実現すること。この二つから、作曲作業にあたっての具体的な個々の音の確定方法が導き出される。