
一度では紹介しきれないほど中身の濃い本である。印象に残ったところと、「重量奏法」について役に立ちそうなところと、2回くらいに分けて書いてみたいと思っている。
[目次]
- ロシア音楽の黎明
- 世界をうならせたロシア・ピアニズム
- 名匠ヴィクトル・メルジャーノフ
- ストレインジ・シューベルト
- 朗読と音楽のコラボレーション
- 身体が生みだす響き
- 響きで創造する
なお、単純な抜き書きの「読書ノート」は下記。
《ノート1:歴史とピアニストの系譜》
《ノート2:重量奏法の秘密》
《ノート3:「ストレインジ・シューベルト」》
《ノート4:「身体が生みだす響き」》
《ノート5:「響きで創造する」》
第一章と第二章は、ロシアのピアノを中心とする音楽家たちの系譜(師弟関係など)や歴史が書いてある。これはこれで興味深いのだが、知らない名前が多くて、基礎知識のない私にとってはちょっと手強かった。次のような記述が続いている。
「ホロヴィッツはキエフ音楽院でレシェティツキの弟子のプハルスキーとエシポヴァの弟子のタルノフスキーに師事した後、ブルーメンフェルトの教えを受けた。…」
それでも、ロシア・ピアニズムの最初にはリストがいるということなど、初めて知る興味深いことも多かった。リストの教えは、例えば次のように広がっていった。
「ハンス・フォン・ビューロー→カール・ハインリヒ・バルト→アルトゥール・ルビンシュタイン、ゲンリフ・ネイガウス、ヴィルヘルム・ケンプ」
「マルティン・クラウゼ→エドヴィン・フィッシャー、クラウディオ・アラウ」
「イシュトバーン・トマーン→バルトーク」
こうやってみると、たんなる昔の人と思っていたハンス・フォン・ビューローなども身近に感じるから不思議なものだ。
ネイガウスに関する話も『ピアノ演奏芸術』を読んでいた(→参考:読書メモ)ので、面白かった。ネイガウスはエミール・ギレリスによって獄中から救われるのだが、音楽に関しては二人の考え方は合わなかったらしい。ちなみに、ギレリスは重量奏法の「お手本中のお手本」だそうだ。
私の好きな作曲家の一人であるメトネルも優れたピアニストでもあったようで、ベートーヴェン「熱情」ソナタの名演奏が残されているとのこと。
ロシア・ピアニズムの歴史以外でなるほどと思ったのは、第四章のシューベルトの話である。シューベルトのピアノ曲はきれいなのだが、同じ旋律の繰り返しが多いのが玉にきずである、と思っていた。そのナゾが少しだけ分かった。
シューベルトの真骨頂は何と言っても「歌」である。「歌曲において言語をそのまま音楽にした。これこそまさにシューベルトの斬新性である」とある。当時は歌詞(言語)にそって、そのイントネーションなどをそのまま音楽にすることは行われていなかった。
そしてもう一つの斬新性が、「こうした抒情的なメロディを器楽曲のソナタ形式の主題に用いたこと」なのだそうだ。最初は、ベートーヴェンのような「分解されたモチーフを再構築して展開する方法」が取れないため、そうとうに苦労したらしい。しかし最後には、メロディを分解せずそのまま器楽曲に取り入れることに成功した、とある。
シューベルトの音楽では「過程こそが大切」で、「結果を急がないシューベルトのピアノ・ソナタは、えんえんと似たようなメロディが続き、あれほどまでに長い作品になったのである」とある。私としては、十分に納得したとは言えないが、そこで引用されていた、ドイツの音楽学者ユルゲン・ウーデの次の言葉は少し分かるような気はする。
「シューベルトの作品はオーストリアの風景に似ている。田園風景を眺めながら歩いていくと、また次の町が見えてくる。それは今までいた町とほとんど変わらない様子を見せているが、それでもやはり違うのだ。われわれはその町を通り過ぎて進んでいく。まるで何事も起こらなかったかのごとく。しかし、そのとき、われわれの内面では明らかに何かが起こっている。それがシューベルトの音楽だ。」
忙しい現代人には「波長」が合わないかもしれない。しかし、もう一度じっくりとシューベルトを聴いてみたいという気持ちにはなった。
次回は、自分自身の練習方法のヒントを得られそうな、「重量奏法」についての話をまとめてみたい。
【関連記事】
《7分で読めるピアノの本(2):ピアニズム》
《7分で読めるピアノの本(1):ネイガウス》
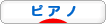
0 件のコメント:
コメントを投稿