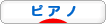第1部「アーティキュレイション」
※第Ⅱ章で、作曲(の方法論)が「楽音の分節」+「楽音の連接」という視点で捉えられることを見た。調性音楽や十二音音楽、総音列音楽などでは「連接方法」が作曲の中心であり、楽音のグルーピングこそが連接の方法論であった。一方、偶然性の音楽においては、連接方法の欠如が聴き手による連接を促す結果を生んでいた。
アーティキュレイション 第 Ⅲ 章
「連接」作業から遠ざかる「作曲」
>半世紀前、伝統的な「楽音」は作曲の前提として安定しており、作曲家の仕事はもっぱら「連接」にあった。しかし、音群的音楽が登場するに至り状況は一変し、作曲は作品の素材となる「楽音(音群)」を分節する・創り出すことから始まることになった。
>音群的音楽の作曲理論の一つであるヤニス・クセナキスの作曲理論においては、もっぱら「どのように音群を作るか」について考察され、「連接」のための方法論を見いだすことはできない。
>作曲が連接作業から遠ざかる傾向は音群音楽だけの傾向ではない。ケージの偶然性の音楽では、作曲家の手による連接はまったく放棄されている。(偶然性の音楽では「音の分節」作業も基本的には放棄されている。)
「楽音(音群)」に対する新たな「連接」の要請
>従来の作曲は、「楽音(調性音楽)」に対する「連接」作業であったが、クラスター音楽(音群音楽)の新しい「作曲」においては「楽音(音群)」を「分節」する作業が中心となる。なお、音群には単純な音(調性音楽における楽音や正弦波など)も含まれる。
>「楽音(調性音楽)」はディジタルに特定することができるが、「楽音(音群)」は特定することができない。音群にも音高感や音色感はあるが、漠然としたものでしかない。したがって、「楽音(音群)」を「連接」するためのこれまでとは異なった方法が必要になるはずである。
「楽音(音群)」に対する「連接」の現実
>しかし、現実に起こったことは、「新たな連接方法」を創り出すことではなく、従来の「連接方法」が適用できるように「個々の音群を調整する」ことであった。例えば、音群を構成する音の要素を少なくしたり、音群内のパラメータ(例:音高)を一つにそろえることにより、ディジタルに捉えることが可能となる。これで、従来の連接方法が適用できるようになる。
>このようにして、「楽音(音群)」にも、ほとんど「楽音(調性音楽)」に近いものから、まったくディジタル的に捉えられない「音の群れ」まで様々な段階のものが存在することになる。
>「楽音(調性音楽)」に近い音は従来の連接方法に近いものを適用することができる。しかし、この方法では、ディジタルに捉えられないものの割合が増えるにしたがって「連接」が弛み、それは単に隣り合う音の接合以上のものではなくなってしまう。
>この「方法論の欠如」により、作曲家は何の手がかりもないなかで、自身の感覚に頼るしかなくなってしまう。これは個人様式化とステレオタイプ化をもたらす。そのため、その音楽はそれぞれの作曲家の「個人言語」(イディオレクト)となってしまう。
「楽音(音群)」に対する「連接」の模索
>(筆者が)1973年に『線の音楽』を作曲し始めたとき(今でも)、音群に対する新たな連接方法を編み出そうとは思わなかった。音群の特性が要請する連接方法への具体的な見通しも持たずに取り組むことは、当時のステレオタイプ化の流れに巻き込まれてしまうと感じたからだ。
>音の分節は、ある連接体系に適合される形で行われるべきであるし、逆に連接方法も、そこで分節される音の特性に根ざしたものであるべきだ。これを一つの「分節=連接」として考えることはできるが、その実現は絶望的に見える。
>こうして音群的音楽が突きつけたのは「一体、どのような音から音楽が可能か」という深刻な課題であった。
>どのような音でも「楽音」化できる状況のなかでのアプローチ方法としては、一度にあらゆる特性の「楽音」を扱うのは困難である。ある「分節=連接」上の視点を設定し、その可能性を認識した上で、そこに含まれなかった素材への有効性を検討していくのがもっとも現実的だろう。
〔第Ⅲ章→ノート3に続く〕