■『バレンボイム音楽論』 読書メモ(9):完
読書メモ(9):完
※目次・紹介は→本「バレンボイム音楽論」:紹介
第2部「変奏曲」 【モーツァルト、ブーレーズ、サイード】
--------------------------------------------------
●抜き書き(数字はページ番号)
【モーツァルト】
…モーツァルトからなにかを学べるとすれば、なにもかもひどく深刻にとる必要なないということだ。どれほど悲劇的な状況でも、どれほど恐ろしい状況でも、あらゆる状況には必ずそれほど深刻でない側面がある。
192
現代では、文明が以前より脆弱で薄っぺらなものになっている。もはや私たちに、自分自身で問いを見出して問いかけるだけの勇気がないせいだ。私たちは答えという観点から考える―しかもさらに悪いことには他人の答えという観点から考える。
195
…時代の流れに順応していない者のほうが、ときにはものごとがよく見えるということだ。
【ブーレーズ】
※現代音楽
バルトーク、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、カバレフスキー、ハチャトゥリアン
210
現代音楽で問題なのは、ほとんどの場合、作品がじゅうぶんな頻度で繰り返して演奏されないことである。この結果、曲にたいして必要な親しみが得られない―なによりもまず、オーケストラが曲にたいする親しみを得られない。…もちろん、聴衆にとっても同様である。
213
彼(ブーレーズ)はまた、20世紀初頭のフランス音楽、なかでもドビュッシーとラヴェルの音楽―二人のうちでもとくにドビュッシー―がたんなる色彩以上のものであり、そこに深さとアーティキュレーションがあることを最初に理解した音楽家のひとりでもあった。…さまざまな点での真の豊かさ…
【エドワード・サイードの思い出】
216
彼は音楽をたんなる音の結合としてだけみるのではなく、すぐれた曲はどれも、いわばある種の世界観であることを理解していた。ただ、この世界観が言葉では説明できないところに―もし言葉で説明できるのなら、そんな音楽は無用だろうから―そのむずかしさがある。けれどもサイードは、それが言葉であらわされないからといって意味をもっていないわけではないことを理解していた。
--------------------------------------------------
●感想など
モーツァルトの章は面白い。とくに「なにもかもひどく深刻にとる必要なない」ということを、モーツァルトから学べるという視点はユニークである。確かにその通りだし、そういう生き方をした方が楽だと思う。
また、「文明が以前より脆弱で薄っぺらなものになっている」という指摘も厳しい。「私たちは答えという観点から考える―しかもさらに悪いことには他人の答えという観点から考える」と、ズバリと痛いところに切り込んでいて、この本の文明論的な要素が感じられる。
現代音楽に関しては、私自身もなかなか理解できないし好きになれないのだが、「現代音楽で問題なのは、ほとんどの場合、作品がじゅうぶんな頻度で繰り返して演奏されないことである」ということは再考の価値があると思う。現代の演奏家・音楽家の人たちに頑張ってほしい。
サイードの章では、「すぐれた曲はどれも、いわばある種の世界観である」という表現が印象に残った。音楽をこういうレベルで聴いたり理解できるように、ぜひなりたいものである。
--------------------------------------------------
『バレンボイム音楽論』 の読書メモ、この稿で完了。もう一度読み返したい。
の読書メモ、この稿で完了。もう一度読み返したい。
※目次・紹介は→本「バレンボイム音楽論」:紹介
第2部「変奏曲」 【モーツァルト、ブーレーズ、サイード】
--------------------------------------------------
●抜き書き(数字はページ番号)
【モーツァルト】
…モーツァルトからなにかを学べるとすれば、なにもかもひどく深刻にとる必要なないということだ。どれほど悲劇的な状況でも、どれほど恐ろしい状況でも、あらゆる状況には必ずそれほど深刻でない側面がある。
192
現代では、文明が以前より脆弱で薄っぺらなものになっている。もはや私たちに、自分自身で問いを見出して問いかけるだけの勇気がないせいだ。私たちは答えという観点から考える―しかもさらに悪いことには他人の答えという観点から考える。
195
…時代の流れに順応していない者のほうが、ときにはものごとがよく見えるということだ。
【ブーレーズ】
※現代音楽
バルトーク、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、カバレフスキー、ハチャトゥリアン
210
現代音楽で問題なのは、ほとんどの場合、作品がじゅうぶんな頻度で繰り返して演奏されないことである。この結果、曲にたいして必要な親しみが得られない―なによりもまず、オーケストラが曲にたいする親しみを得られない。…もちろん、聴衆にとっても同様である。
213
彼(ブーレーズ)はまた、20世紀初頭のフランス音楽、なかでもドビュッシーとラヴェルの音楽―二人のうちでもとくにドビュッシー―がたんなる色彩以上のものであり、そこに深さとアーティキュレーションがあることを最初に理解した音楽家のひとりでもあった。…さまざまな点での真の豊かさ…
【エドワード・サイードの思い出】
216
彼は音楽をたんなる音の結合としてだけみるのではなく、すぐれた曲はどれも、いわばある種の世界観であることを理解していた。ただ、この世界観が言葉では説明できないところに―もし言葉で説明できるのなら、そんな音楽は無用だろうから―そのむずかしさがある。けれどもサイードは、それが言葉であらわされないからといって意味をもっていないわけではないことを理解していた。
--------------------------------------------------
●感想など
モーツァルトの章は面白い。とくに「なにもかもひどく深刻にとる必要なない」ということを、モーツァルトから学べるという視点はユニークである。確かにその通りだし、そういう生き方をした方が楽だと思う。
また、「文明が以前より脆弱で薄っぺらなものになっている」という指摘も厳しい。「私たちは答えという観点から考える―しかもさらに悪いことには他人の答えという観点から考える」と、ズバリと痛いところに切り込んでいて、この本の文明論的な要素が感じられる。
現代音楽に関しては、私自身もなかなか理解できないし好きになれないのだが、「現代音楽で問題なのは、ほとんどの場合、作品がじゅうぶんな頻度で繰り返して演奏されないことである」ということは再考の価値があると思う。現代の演奏家・音楽家の人たちに頑張ってほしい。
サイードの章では、「すぐれた曲はどれも、いわばある種の世界観である」という表現が印象に残った。音楽をこういうレベルで聴いたり理解できるように、ぜひなりたいものである。
--------------------------------------------------
『バレンボイム音楽論』
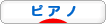
0 件のコメント:
コメントを投稿