マルタ・アルゲリッチの伝記(2009年まで)『マルタアルゲリッチ 子供と魔法』という本を読んだ。アルゲリッチについての、おそらく世界初の伝記とのこと。
面白くて、こんなにオープンに書いていいのだろうかということが次から次へと明かされて…、久しぶりに一気に(といっても3日くらいで)読んでしまった。

(音楽之友社、2011年、オリヴィエ・ベラミー著、藤本優子訳)
こういう本は、サマリー的な紹介は書けないし、感想を書くにもいろんなことがありすぎてまとまらない。
本人の生い立ちや生き様から家族模様、ピアニストとしての興味の尽きないエピソードの数々、なぜあのように弾けるのかという謎を解き明かすヒントになりそうなこと、登場する「キラ星」のような多くの音楽家たち、彼らとの関わり方、などなど…。
盛りだくさん過ぎるので、「伝記」の本筋とはちょっと外れるかも知れないが、面白いと思ったことをいくつか書いてみたい。
スカラムッツァ先生
アルゲリッチが5歳半〜11歳の間ついていた先生がヴィンチェンツォ・スカラムッツァという人。その人の考え方がとても共感できる。
「スカラムッツァが純粋にテクニックのためだけの練習曲を与えることは決してなかった。音階、アルペッジョ、その他の指回りのことは古典作品によって身につけることができる、そう判断していた。モーツァルトのソナタやショパンの練習曲で、そういった技巧的に華やかな部分だけを曲の内容から切り離して見ることはできない。それどころか、エクササイズによって技巧が味気なくなり、指さばきの鍛錬で、身につくはずの音楽性が損なわれてしまう。…」
「一つの音の成立には三つの段階がある…。まず筋肉を弛める。その状態から瞬間的に指先の肉を通じて重さが伝わる。次に跳ね返り(バウンド)。屈筋の収縮を受けながら弾んでくる。最後が動きの中断による休み。」
これは、なんとなくアルゲリッチの弾き方を彷彿とさせる。著者も次のように書いている。
「鍵盤上を疾走するマルタ・アルゲリッチの手は、緊張とリラックス、正確さと移動スピード、その同時性のみごとな実例であり、ピアノ演奏のテクニックの試金石だ。」
憧れのホロヴィッツとの共通点
「ホロヴィッツならではの柔軟な指さばき、…特にきわだった電気的な要素、桁外れにパワフルなオクターブ、フレーズのイマジネーション、この世のものとも思われないピアニッシモ、内声部に息づく密やかな生命力、無限のニュアンスを生みだす能力。いずれも彼女(アルゲリッチ)自身の演奏を形容する言葉である。」
「ホロヴィッツはシューマン作品の天才的な奏者であり、その点でもアルゲリッチの"分身"だ。そしてホロヴィッツのスカルラッティとアルゲリッチのバッハが、録音された音楽の頂点をきわめるものだという意味で、両者ともたぐいまれな"古典派"でもある。」
本に登場する印象的な言葉
●身体の内なるものを治すのが医師だとすれば、魂の痛みをやわらげ、慰めを与えるのが芸術家である。
アルゲリッチは医者になりたいと思っていた時期があるそうだ。プルーストの質問表の「持ちたい才能は何か」という問いに対して「治癒の力」と答えている。
伝記の中に、弱者や困っている人を見たら支援の手を差し伸べずにはいられないアルゲリッチが何度も出てくるが、その姿と「魂の痛みをやわらげ、慰めを与える芸術家」とがオーバラップして感じられる。
●マルタはショパンの練習曲を完璧に弾きながら、同時にオスカー・ワイルドやアレクサンドル・デュマの本を読んでいた…。(弟カシケの証言)
さすが!すごい!ハノンとかじゃなく「ショパンの練習曲」!
●(私は)人のために演奏しているのではない。自分のため、作曲家への奉仕として弾いているのだ。聴衆がいようがいまいが大したことではない。ピアノに向かうとき、頭にあるのは精神の産物としてそこから生まれてくる響きのことだけだ。(ミケランジェリの言葉)
芸術家の中には、こういう極端な考え方の人もいていいと思う。最近の「アーティスト」の中にはこの真逆の人が多過ぎるような気もする。
●偉大な芸術とは時を超越したものであり、偉大な様式はつねに隠れたところにある。つまり、これ見よがしの様式は誤りなのだ。昔の人はあまりにわかりやすいものを好まなかった。様式と言われるものは、たいていはその時点の流行でしかない。(フー・ツォンの言葉)
ちょっと難しい。「様式」とはバロックとか古典派とかロマン派とかじゃないのかな?
1957年のジュネーヴ・コンクール
16歳のアルゲリッチと15歳のポリーニが参加したときのジュネーヴ・コンクールの審査方法が面白い。
「音楽以外の要素による影響を避けるため、出場者たちは姿が見えないように幕を張った向こう側で演奏させられた…」
しかも男子と女子とは別部門として審査する。
結果、アルゲリッチは女子部門の1位、ポリーニは男子部門の2位となっているが、二人の間の順位(優劣)は分からないということだ。
ちなみに、現代のコンクールでも「幕の向こう側」方式を採り入れたらどうだろうと思った。そうすれば、オーバーアクションの印象とか見かけの良し悪しとかが排除される。ついでに名前も伏せて行えば、妙な「政治」もやりづらくなると思うのだが…(^^;)。
聴きたいと思った録音
●チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番
1970年にシャルル・デュトワが無理に説得して弾かせたもの。ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団。
「…あれほどの狂気、あれほど楽器の限界を超えた演奏で聴かせた者はいない。あれはヴィルトゥオーソを凌駕した何かだ」と評された。
●スティーヴン・コヴァセヴィチと共演した唯一のレコード
1977年。曲目は、ドビュッシー《白と黒で》、バルトーク《2台のピアノと打楽器のためのソナタ》、モーツァルト《アンダンテと変奏曲》。
これを機に、アルゲリッチはこのジャンルに惹かれるようになった。また、「自分が支援している若いピアニストたちとの演奏機会」を積極的に作るようになった。
●1983年:最後のソロアルバム
シューマンの《クライスレリアーナ》と《子供の情景》。
「彼女は41歳で、リサイタルでの緊張を強いられるのはもう勘弁してほしいと思っていた。『ピアノを弾く機械にはなりたくないのです』と、1986年にアルゼンチンのラ・ナシオン紙で宣言した。『ソリストは一人で生き、一人で弾き、一人で食事し、一人で眠ります。わたしはそんなのは願い下げです。』」
●アレクサンドル・ラビノヴィチとの共演
2台ピアノと4手の演奏が、テルデックから数枚出ていて、いずれも傑作。ラフマニノフ、モーツァルト、ラヴェルなど。
ラビノヴィチとは1987年に知り合って10年ほど付き合っている。ラビノヴィチは、作曲家でもあり、その作品の一つ《時間(ディ・ツァイト)》で、2000年にチェレスタ・パートをマルタが弾いている。
おまけ:『アルゲリッチ 私こそ、音楽!』
この本を読んだあと、2014年にラフォルジュルネで観た『アルゲリッチ 私こそ、音楽!』(原題:"Bloody Daughter")という映画を思い出した。
この映画でも一人の人間(母、祖母)としてのアルゲリッチが、実に魅力的に記録されていたのだが、今回読んだ本では、さらに、娘、友人、恋人、妻、生徒などとしてのアルゲリッチがとても豊かに描かれている。
参考:DVD(たぶん日本語字幕付き)

【関連記事】
《秀逸!人間アルゲリッチを描き出したドキュメンタリー映画》
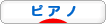
0 件のコメント:
コメントを投稿