『作曲家から見たピアノ進化論』からの話題、第3弾である。
今回は、作曲者が楽譜につけた演奏記号(強弱・速度・アーティキュレーション等)の話。時代により、作曲家により、それをどう解釈するかは当然ながら異なってくる。
モーツァルト:2種類の記譜法
モーツァルトの最初のピアノ・ソナタ K.279〜284は、1775年(19歳)ミュンヘン滞在中に作曲された。これらは、おそらくピアノ向けに書かれたのではないかと、筆者の野平一郎氏は考えている。
「これらのソナタに見られる一音ごとの f と p の交代、一つのフレーズ内での強弱とアーティキュレーションの細やかな記譜、そして緩徐楽章における繊細な感情的変化の表出など、ピアノにとっての理想的なエクリチュール(書法)が取られている。」
つまり、モーツァルトはピアノという楽器の特性を考えながら、あるいは最大限に活用しながら、自らの楽想を記譜していったということである。
野平氏は、モーツァルトが演奏家でもあったことから、出版譜に書き込まれた多くの演奏記号については2種類のものがあると考えている。
「一つは、基本的になくてはならない強弱やアーティキュレーション。絶対に守られなければならないニュアンスである。…彼がもともと作曲時に考えていたそれである。」
「もう一つとは、モーツァルトが演奏の時に作品を活かすために瞬間的に必要だと考えた強弱やアーティキュレーションである。」
そして、後者に対しては、厳密に守るよりも、それがなぜ付け加えられたかという「意味」を考えることがいっそう重要だ、と述べている。
…なるほど、と思いつつ、その2つを楽譜からどう読み取って区別するのかは、少なくとも初心者には至難の技である。(まぁ、区別できたとしても、私のレベルでは、自分自身の弾き方にそれほど影響あるとは思えないが…)
ベートーヴェンのペダル記号
ベートーヴェンの時代には、かなり現代ピアノに近いものが作られていた。ベートーヴェンは、そのピアノの性能をフルに活かして、あるいはそれを超えるイマジネーションを持って、多くのピアノ曲を書いた。そして、彼は初めて、音楽に「音響空間」という概念を持ち込んだと言えるだろう。
それは、和音の厚みや広がりであったり、音域の幅であったり、ペダルによって作られる響きであったりする。
ただ、ペダルの扱いには注意が必要だ。なぜなら、当時のピアノのペダルは音の減衰が早い(持続時間が短い)のである。また、楽器自体の倍音構造が貧弱である(現代ピアノに比べて倍音が少ない・小さい)ため、ペダルによる音の重複効果もかなり違っていたはずなのだ。
したがって、ベートーヴェンの記譜に忠実にペダルを踏むと、必要以上に「不協和」な響きになる可能性がある。「これを演奏でどのように処理していくかは、各ピアニストに課された大きな課題である」とのこと。
まぁ、初心者の立場としては、そこまで気を使う余裕はないのだが、少なくとも音楽鑑賞において「このピアニスト、ちょっとペダル踏みすぎなんじゃないの?」くらいは分かるようになりたいものだ。
シューマンのアクセント記号
ショパンやシューマンのような「ロマン派」の作曲家・作品について、野平氏は面白い表現を使っている。
「こうした胸の内の不安定さ、移ろいやすさは、従って瞬間を生きることと同義になる。『全体』の構成よりも、『瞬間』が最も貴重なものとなった。そう、まさにロマン派の作曲家たちは『瞬間芸』の作曲家なのだ。」
その「瞬間芸」は楽譜にも表れている。なかでも、シューマンについては、その「内面の複雑さを最もよく表しているのが彼のピアノ作品」であり、彼の楽譜には極めて多くの繊細な演奏・表情記号が書き込まれている、とのことだ。
シューマンほど、大量かつ多様なアクセント記号を書いた作曲家はいないらしい。「>」「Λ」「 f 」「 sfz 」等々。
それらがつけられた意味を文脈の中で理解し、それぞれに適切な表現を探していくことが、シューマンの音楽に迫る一つの方法になるだろう、とこの本の筆者は述べている。
感想:そうだったのか…。私の場合、有名な作曲家の中で、いまひとつ理解できないのが、シューマン、シューベルト、ブラームスあたりである。「内面の複雑さ」がその理由の一つかもしれないと思いながら、次にシューマンの楽譜を見るときはアクセント記号に注目してみようと思った次第である。
【関連記事】
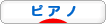

0 件のコメント:
コメントを投稿