面白くて一気に読んでしまった。日曜日(8/21)の「題名のない音楽会」で(恥ずかしながら…)初めて知ったのだが、第20回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した本だそうだ。

この本は、基本的には1986年の第8回チャイコフスキー・コンクールの審査の流れに沿って、審査員やピアニストや審査の内容や期間中の生活や…、等々を審査員&ピアニストの視点から、いろいろと脱線しながらも実に面白く、臨場感豊かに書いてある。
人間味あふれる審査員の描写など実に興味深い。自分の教え子に前日までレッスンをして何とか入賞させようとしたり、美人ピアニストに胸踊らせたり?する、音楽院の老教授人たち…。
一方で、コンクールのあり方やピアニストの進路?などについても、いろんな問題提起もある。
何年かに一度の天才発掘ではなく、それなりに上手い「万能型」のピアニストを選ぶ場にならざるを得ない状況。入賞者が、コンサートやメディアに追い回され「消耗」していく状況。需要に対してピアニストが多すぎるという問題…。
そういったことが、この本の主題なのだとは思うが、ここでは、個人的に興味をもったことを少し書いてみたいと思う。
コンセルヴァトワール
音楽院のことを「コンセルヴァトワール」(conservatoire、conservatory)と呼ぶことに何となくしっくりきていなかったが、この本で少し分かった気になった。
意味としては「保守的」みたいなこととは少しニュアンスが違っていて、「伝統の保存」みたいなことのようだ。
ヨーロッパでは音楽に限らず、「伝統のある規範や基本を徹底的に踏襲させることが教育の基礎であって、独創や改革はその基礎があってこそ開花する」という信念があるということだ。
ピアノ教育においては、基本的には「19世紀に爛熟完成をみたピアニズム」(ロマンティシズム)の継承を中心とすることになる。
それを象徴する言葉として、「ショパン(あるいはロマン派の作品)を聴くまで、その(ピアニストの)才能に決定的評価を下すのは待て」というのがあるそうだ。
そして、「ショパンが弾ける者にはバッハもベートーヴェンもあるいはいっそジョン・ケージまで弾ける可能性があるが、その反対はまず起こらない」と書いてあるのだが、この点に関しては少し違和感がある。
素人考えでは、ケージとか現代曲のいい演奏がなかなか見つからない理由の一つは、現代ピアノ曲に対する適切なピアニズムがいまだ確立されてないことがあるのではないかと思う。新しい時代の新しいピアノ曲には、それにふさわしい解釈やピアノ奏法があるのだと思う。
それにしても、伝統の積み重ねがあるヨーロッパでは「コンセルヴァトワール」は成立するのであろうが、日本ではなかなか厳しいのではないかと思った。現在でも、基本は「文明開化」「西洋に追いつけ追い越せ路線」の延長でしかないように感じてしまう。
日本のピアニズム?
欧米と日本のピアノ教育の違いはいろいろあるようだが、欧米のコンセルヴァトワール(音楽学校)には男性が多いことも大きな違いだそうだ。
そもそも、「ヨーロッパ人にとって音楽とは宗教的尊厳(即ち神)そして世俗的尊厳(即ち君主)の象徴とみなされてきたものであり、要するに権力、男らしさ、英雄的なもの等々の象徴であった」とのこと。チャイコフスキー・コンクールも、始まったころは女性は参加できなかったらしい。
でも、逆に日本では女性が多いのはなぜなんだろう? 職業ピアニストというより、ショパンの時代の「良家の子女の教養」的要素が強かったのだろうか?
で、その日本でのピアノ教育の問題として「ハイフィンガー奏法」(の影響)が言われることがある。さすがに現在ではないのかな、とも思っていたのだが…。
そのあたりの、中村紘子さんの説明が面白い。
「しかし、指と指の間の筋肉を鍛え、その一本一本の自立を促す一種の訓練法としてはなかなか効果があって…」
「…非音楽的ではあったけれども他方では、特に子供たちが『しっかりと』手先の筋肉を鍛え、『バリバリ』弾けるようになるには手っとり早い、という利点があった」
こういう弾き方は(この本が書かれた1988年からみても)「もうずいぶん昔のこと」で、改善されているはずであるが、コンクールなどでは、審査員にいまだに先入観が残っているのではないか、というのが著者の指摘。
日本人は、
「一つのミスもなく平然と演奏するが、機械のように無表情である」
「きちんと弾くが個性に乏しい」
といった先入観が…。
ただ一方で、このコンクールには、岡田博美、小川典子、田中修二の3氏が参加していたのだが、その演奏に対する中村紘子さんの評価は、
「ハイフィンガーの影響、ロマン派的振幅が小さい、音もきゃしゃで平板で単色であり、感情が率直に伝わってこない、もっと文学的感受性が備わっていたなら…」
などというものであった。
少なくとも1988年には「ハイフィンガーの影響」は、完全に払拭されるには至っていなかったように見える。
「これは、日本人の西洋音楽に対する基本的な感受性の有無に関することなのであろうか。それとも、知性や感受性といったものを論議する以前の、ごく具体的にいって「表現技術」に類する問題なのであろうか」
…と、中村紘子さんでさえ疑問形で結んでいる。
「音楽的」とは?
「音楽的」という言葉はかなり曖昧なものだと思うが、「教育やコンクール…における『音楽的』という言葉」を説明したくだりは面白い。
「分かり易くいうと…『恣意的』あるいは『出鱈目』な演奏と対比する意味で使われる」
「…『音楽的』にうたって演奏することと、勝手気ままに『出鱈目』に弾くことが混同される…」
要するに「音楽の構成や様式や演奏上の約束事」を踏まえずに、勝手にテンポをゆらしたり、ルバートするピアニストが多くて、それは「出鱈目」というわけだ。それに対して、きちんとテンポを維持し、その曲にあった歌い方ができれば「音楽的」となる。
音楽的な演奏のためには、例えば、
「モーツァルトの演奏とラフマニノフにおける演奏とでは、打鍵の指の角度、深さ浅さ、手首の高さ低さ、力の入れ方抜き方、更には全身のピアノに向かってのフォームまで、必然的にことごとく違ってくる」
といった「奏法のディテール」を一つ一つ踏まえるということが必要になる。
それができない、「ベートーヴェンを船酔いしそうなテンポ・ルバートで」弾くような弾き方が「出鱈目」となる。
そして、「先生たち(審査員自身もそうだったりする…)は何をしているのだろう?」と問いかける。こういう「出鱈目」を修正するのはピアノ教育では基本的なことだからだ。
コンクールでそういう弾き方を多く見るということは、そういう弾き方をする生徒を「権威をもって指導する」「説得力をもって(その理由を)説明する」ことができない教師がいることを物語っている…。
…なるほど、コンクールで審査員はそういうところを(も)見ているのか、と思うと同時に、この「音楽的」というのは最低ラインの「音楽的」なんだろうなぁ、とも思った。
これで、とりあえずの中村紘子さん追悼読書?は終わりとする。もっと早く、少なくとも去年のチャイコフスキー・コンクールの前に読んでおけばよかった、と思ったがそれは後の祭り…。
改めてご冥福をお祈りする。
【関連記事】
《ピアノコンクールの意義?「コンクールでお会いしましょう」》
《読書メモ:ピアニストだって冒険する》
《『キンノヒマワリ』中村紘子の記憶》
《「ピアニストという蛮族がいる」やっと読んだ…》
《「ピアニストは半分アスリートである」の裏付け?》
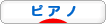

0 件のコメント:
コメントを投稿