タイトルだけは知っていて、そのうち読もうかとずっと思っていて、結局、読むきっかけが著者の逝去というのも、何となく申し訳ないような気もしながら、やっと読んだ。
中村紘子さんの『ピアニストという蛮族がいる』という本である。

紹介文にある「ホロヴィッツ、ラフマニノフほかピアノ界の巨匠たちの、全てが極端でどこか可笑しく、しかも感動的な“天才ぶり”を軽妙に綴った」部分も、エピソードてんこ盛りで結構面白かった。
…のだが、個人的には日本の草分け的な女流ピアニストの一人である久野久(くの ひさ)と、オーストラリア出身の美人ピアニスト、アイリーン・ジョイスの波瀾万丈な話が印象に残った。
草分けピアニストの悲劇
久野久は1886年生まれで、小さいころは邦楽をやっていたが、15歳で東京音楽学校に入りピアノの勉強を始める。当時の教育環境は相当に貧弱で、ピアノは学校にしかないし、教師も海外から来た三流の怪しげな「ピアニスト」。
日本人特有の勤勉さで身につけた「奏法」は、「ハイ・フィンガー」で激しくピアノを「ぶっ叩く」弾き方。演奏会では、「髪が乱れ、かんざしがふっとぶ」ほどの激しい動きでベートーヴェンを弾く。
まるで見世物を見るような当時の聴衆はその姿に歓喜し、日本随一のピアニストになってしまった。30歳で教授にもなっている。これが悲劇の始まりである。
日本一のピアニストとなった久野久は、欧州遠征に赴くことになる。
が、演奏会は思うようにできず、弾き方はことごとく否定され、ケンプやブゾーニの演奏を聴いて衝撃を受け…。ついには、ウィーンのホテルの4階屋上から投身自殺をしてしまう。このとき38歳……。
これを読みながら、この悲劇の背景にあったものは、日本のその後のピアノ界にも影響しているのでは、と思った。門外漢の邪推かもしれないが、久野久の時代の空気が、現在の日本のピアノ教育界にもまだ幾分残っているのではないか?ということ。
邦楽の家元制度のような「門下制」?、どこか未だ断ち切れていないかもしれない「ハイ・フィンガー奏法」の影響?、刻苦勉励型のメカニック練習など、…いや邪推であればよいのだが…。
カンガルーと育った天才ピアニスト
話はガラッと変わって、最近「シドニー国際ピアノコンクール」、「アルゲリッチ、オーストラリア・デビュー!」と、なんとなく盛り上がっている?オーストラリアに飛ぶ。
かつて、オーストラリア出身のアイリーン・ジョイス(Eileen Joyce、1908 - 1991年)という、美人ピアニストがいたという話なのだが、その生い立ちが変わっている。
彼女は、オーストラリアでもさらに南の離れ島、タスマニア島でカンガルーを友としていた野生児であった。子供のとき出会った音楽といえばハーモニカくらい。
その少女が、引越した田舎町の学校の片隅で尼僧が教えるピアノに出会い、瞬く間に才能を開花させていく。
そして、かのバックハウスに見出され、ライプツィヒ音楽院で本格的にピアノを始めたのが14歳。ところが、さすがに周りの秀才たちにはかなわず悶々としながらも、猛勉強を続ける。
そんな中「4年も経つがどうしている?」という父親の手紙に、自分の演奏を録音して送ろうと考えたところから彼女の運が開けていく。
当時、グラモフォンが素人相手の「レコード録音サービス」のようなものをやっていて、そこで彼女の素晴らしい演奏を聴いたグラモフォン社はすぐに契約を申し出た。
無名の18歳のピアニストがいきなり(今なら)「CDデビュー」というすごいことになったわけだ。
その後も、美人ピアニストとして活躍するだけでなく、映画プロデューサーでもある資産家クリストファー・マンと出会い、結婚し、彼の映画に出演するようになり…。
…と順風満帆に見えたが、1963年突如引退。神経過労が原因だった。
中村紘子さんによると、「アイリーン・ジョイスは、その余りの美貌ゆえの毀誉褒貶によってピアニストとしての評価を歪められ、開花成熟への道を自ら閉ざしたかに見える」とのこと。
美人ゆえの人気か、ピアノの実力での人気か、といったことは現代でもいろいろありそうだ…。
ちなみに、彼女はシドニー国際ピアノコンクールの審査員もつとめたことがあり、たしかに "Previous Competitions" のページの1981年と1985年のところに "Eileen Joyce" の名前が載っている。
【関連記事】
《ピアノコンクールの意義?「コンクールでお会いしましょう」》
《中村紘子さんの「チャイコフスキー・コンクール」面白い!♪》
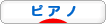
0 件のコメント:
コメントを投稿