先月の記事、《本『これを聴け』を読んではみたが…》でご紹介した、アレックス・ロス著の「音楽書としては異例の世界的ベストセラー」が気になっていた。
で、その本(の2巻のうち1巻)『20世紀を語る音楽(1)』を、ようやく読み終えた。読み応えのある(時間のかかる…)本である。

音楽界の潮流、音楽作品そのもの、作曲家のおかれた社会的な環境や初演の状況、他の作曲家や芸術家との交流や軋轢など、実に多様な切り口から描かれており、20世紀のクラシック音楽がどこへ向かうのかを明らかにしようとした力作である。
楽譜や演奏から見える作曲家ではなく、当時のいろんな状況の中で生身の作曲家がどんな思いでその曲を書いたのかなど、当時の「リアルなクラシック界」のようなものがうかがい知れる本だ。
本当は、その「圧巻の20世紀音楽史」を読み取って、ここに紹介できればいいのだろうが、それは至難の技である。なので、読書感想文的に、読みながら感じたことなどをいくつか書いてみたい。
「クラシック音楽」とは?
まず、全体を通して感じた疑問、というか居心地の悪さのようなもの。
一般的にそうなのだが、「クラシック音楽」というとオペラ(や大規模オーケストラ作品)がかなり主要な位置を占める。音楽雑誌や音楽鑑賞付き海外ツアーなどでもそうだ。この本も、R・シュトウラスの『サロメ』で音楽界が大きく変わった、時代が進んだという話から始まる。
個人的にオペラがあまり好きではない(聴かない)こともあり、この手の音楽史には違和感がある。もちろん、モーツァルトのオペラの中にはいい曲もあるし、ショパンも大のオペラファンだったのだし、世の大勢がそうなので、こちらの問題だとは思うのだが…。
それでも、例えば、学校で習った音楽史(バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン…)の流れと、オペラが重要な位置を占めているような記述の間には大きなギャップを感じる。
音楽そのものを聴いても、例えば、オペラとピアノ音楽との間には、交響曲とポピュラーミュージックくらいの差があるように感じてしまう。あるいは、オペラはどちらかというと演劇とか舞台芸術であって、音楽はその構成要素の一つ、という感覚…。
世の中には実に多様な「音楽」がある。オペラ、オーケストラ、室内楽、器楽ソロ、ブラスバンド、ジャズ、ダンスミュージック、シンセサイザー、合唱、歌曲、歌謡曲、フォーク、ロック、ポップス、邦楽、民族音楽、コンピュータミュージック、…。
一方で「音楽」ってそもそも区分はなくひとつのもの、という考え方もある。「クラシック音楽」と言われるものにも、民族音楽とかジャズと融合したような音楽もたくさんある。
…ん〜、少し頭が混乱してきた。「クラシック音楽」とは何?
シリアスな音楽とポピュラーな音楽?
「クラシック音楽」とは何か、ということにも関連するのだが、この本のあちこちに出てくる議論?が「シリアスな音楽 v.s. ポピュラーな音楽」という対抗軸?である。それと同じような話が「進歩・新規性があるかないか」という視点。
この本の「はしがき」に次のようなことが書いてある。
「進歩という概念が過度に重要性を帯びると、これといった新しいことがないという理由で、多くの作品が歴史的な記録から外されてしまう。こうした作品はしばしば幅広い聴衆を獲得した作品と一致する。…」
こうした作品の例として、シベリウスやショスタコーヴィチの交響曲、コープランドの《アパラチアの春》、カール・オルフの《カルミナ・ブラーナ》があげられている。
個人的に、より問題だと思うのはその逆で、新規性があるというだけである作品が高く評価されることだ。現代の「作曲業界?」は、どうもそういう風潮があるような気もしている。一般聴衆としては、評論家のそういう評価は迷惑だ…。
こういう状況は、ずっと(おそらく現代まで)続いているようで、この本にもいくつかそういう記述がある。
「マーラーはシュトラウスが卑俗な趣味へと走ったと非難した。二人の間の亀裂は、作曲家の役割をめぐって、近代主義的な考え方と一般大衆向き(ポピュリスト)の考え方とで、20世紀の音楽にさらに大きな分裂が生じることを予告していた。」
そのマーラーも悩んでいたようで、「本当の芸術家でありながらその時代に名声を得ることはできるのか?」といった言葉を残している。
アイヴズの言葉、「…芸術が誕生するのは、芸術で生計を立てることを望む最後の人間がいなくなったとき…だろう。」
それにしても、「クラシック音楽」は「シリアス」でなくてはならないのだろうか?一般大衆に賞賛されることは「クラシック音楽」にとってマイナスなのだろうか?現在、我々が聴いて楽しんでいるクラシック音楽の中にも初演当時に喝采をあびたものがたくさんあるはずだ。
問題は、現代の作曲家がそういう作品をなかなか書けなくなっている状況のように思える。(私が知らないだけ…?)もちろん、作曲家だけの責任ではなく、音大、作曲コンテスト、評論家、演奏家、演奏機会を提供しないシステム、聴衆などにも多くの課題がありそうだ。
されどシェーンベルクは偉大だった?
シェーンベルクの音楽はよく分からない、いまだに好きになれない。音楽史上の重要性は少し分かる気もするし、12音技法というのも必要な「実験」だったとは思うのだが…。しかし、この本にはシェーンベルクの名前が何度も出てくる。それだけ重要な存在ではあるのだろう。
「シェーンベルクがとった手段はきわめて過激であり、…重要なのは、…引き返すことのできない進歩の理論に着手したことである。…シェーンベルクの威圧的な力が初期の聴衆に与えた恐怖…」
「21世紀が始まったいま、シェーンベルクの音楽はもはやそれほど耳慣れないものには聞こえない。…ジャズのビバップや映画のサウンドトラックに新たな道を見出している。」
無調音楽は、様々な作曲家たちが独自にそれぞれの道を目指した(一つのムーヴメントがあったわけではない)。イタリアの未来主義者、超絶主義の影響を受けたチャールズ・アイヴズ、またブゾーニの『新音楽美学構想』(1907年)による理論化など。
その中で、シェーンベルクだけが『和声学』のなかで初めて「調性の死」を宣言し、後戻りがないことを主張した。それに対し、ブゾーニは古いものと新しいものは共存できるのであって、古いものを拒否して新しいもので置き換えようとするシェーンベルクのやり方を批判した。
晩年のドビュッシーは、シェーンベルク(とR.シュトラウス)を「偽の偉大さと整えられた醜さ」と非難していた。そうして、ドビュッシーは「正統的な古典的形式を使うことへの抵抗をやめて、…ソナタの連作にとりかかり…」、「ヴァイオリンのための一曲、チェロのための一曲、フルート、ヴィオラ、ハープのための一曲」の3曲が完成した。
有名人たちの関わり合いが面白い
この本には、R.シュトラウスとマーラーのライバル関係とか、シェーンベルクに対する他の作曲家たちの関係とか、音楽家あるいは人間としての様々な関係が描かれていて面白い。有名人どうしの思わぬ関わりなども出てきて「へ〜っ」と思ったりする。二つほどご紹介すると…。
1917年に、ロシア・バレエ団がパリで《パラード》という「騒々しいサーカスのような公演」を行った。そのときの参加者の名前がすごい。
「エリック・サティが音楽を書き、ジャン・コクトーが台本を作り、パブロ・ピカソが舞台装置と衣装をデザインし、レオニード・マシンが振り付けをし、ギヨーム・アポリネールがプログラム・ノートを書き、ディアギレフがスキャンダルを提供した。」
さすがに振付師の名前は知らないが、豪華な顔ぶれだ。ピカソの舞台装置は見てみたいものだ。ちなみに、この中でアポリネールが「シュルレアリスム」という言葉を発明したようだ。
もう一つは、米国、ビヴァリーヒルズの話。ここには、1930〜40年頃、いろんな亡命作曲家が住んでいた。ストラヴィンスキーとか、ラフマニノフとか…。
その中のエピソードで面白かったもの。シェーンベルクは1934年からロサンゼルスに住んでいて、フォードのセダンを得意げに乗り回し、ガーシュインのテニスコートでチャップリンと下手なテニスをしたこともある…らしい。へ〜っ!(^^)!
以上、感想文。
…さて、この本は2巻構成の1巻目。ということは、もう1冊、『20世紀を語る音楽(2)』というのがある。読み応えがありすぎるので、もう少し時間をおいてから読むことにしようか…。

【関連記事】
《本『これを聴け』を読んではみたが…》
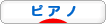
0 件のコメント:
コメントを投稿