ラ・フォル・ジュルネに行って、そのレポートなどを書いているうちに、少し前に読んだ『どこまでがドビュッシー?』(青柳いづみこ著)という本の読書メモを書きそびれてしまった。
読んだ内容の記憶も薄れてきたので、今回は感想文のような随想のようなものを書くことにしたい。

この本は「音楽というのはどこまでデフォルメしたらその音楽に聞こえなくなるのか。ピアニストはどこまで楽譜から自由になれるのか。」といったテーマを、ピアニストの立場から取り上げたものである。
主なテーマの一つは、ドビュッシーの残したスケッチなどの「作品の断片」から「補筆完成」させた「作品」は、どこまでドビュッシーの音楽なのか?ということである。
いづみこさんは、具体的な例をあげながら、行きすぎた「補筆完成」には疑問を呈している。一方で、機械的に補筆したものは面白みに欠ける、ということも言っている。
ところが、残っているドビュッシーの演奏を聴くと、作曲家自身、楽譜どおりに弾いていないところがあったりするらしい。
この問題は、話としては面白いのだが、あまり気にしないでもいいのかな?と思う。ジュスマイヤーによって補筆完成させられたモーツァルトのレクイエムはどこまでモーツァルトか?という問いかけはあまり重要ではなく、その演奏にどれほど感動できるか、が重要なのだと思う。
そもそも、一つの「ドビュッシーらしさ」というものが存在するのかどうか。人によって、その受け取り方は様々だと思う。むしろ、気をつけなければいけないのは、「印象派」などのレッテルをつけて音楽を聴くことだ。先入観なしに、音楽と素直に直接に向き合いたいと思う。
もう一つのテーマは、「演奏者はどこまで楽譜に忠実であるべきか」、言い換えると「演奏者はどこまで楽譜から外れてもいいのか」という問題である。
バッハの時代には、装飾音符は演奏者の腕の見せ所として、「趣味の良い」範囲であれば自由につけることができた。繰り返しのところでは1回目と同じに弾いてはいけないという暗黙のルール?もあった。
「楽譜通りでない」ものをリストアップしてみると結構ある…。
- 自作カデンツァを入れる(協奏曲など)
- 装飾音符を変化させる(バッハの作品など)
- 繰り返しを省く(ゴルトベルクなど)
- テンポを指示通りに弾かない(グールドなど)
- 強弱や奏法の指示を守らない
- オクターブ上/下の音を追加する
- 楽譜にないパッセージを挿入する
- ジャズ的即興(大西順子のラプソディー・イン・ブルー)
このあたりは、聴き手の好み、音楽に何を求めるかによっても考え方が変わってくると思う。ピアニストからすると、表現したいものが作品の枠からあふれ出してしまう場合もあるのだろう。
個人的には「自由な」ピアニストの方が好きかもしれない。音楽を聴いているとき、楽譜のことはほとんど考えない。いい音楽・演奏を聴きたいと思っているだけである。私の場合、「いい音楽」の中に「面白さ」も少し混じっている。
そもそも、どのピアニストの演奏も「楽譜通り」の統一規格になってしまっては面白くない。ピアニストは「ピアノ演奏の職人」というより「音楽を届ける芸術家」であってほしいと願う。最近、ファジル・サイのような作曲するピアニストが少しずつ増え始めているような気もする。喜ばしいことである。
そして最後に「楽譜の向こう側」という話になる。グレン・グールドについての次のような逸話が紹介されている。
13、4歳の頃、モーツァルト「フーガ K394」を練習していたとき、家政婦がかける掃除機の音で自分の弾いている音が少しも聞こえなくなった。そのときグールドは「モーツァルトのもとに降り立った霊感」を聞いたと思った。 … こうしてグールドは、「想像力という内なる耳で聴く」ことを学ぶ。内なる耳で聴く音楽は、楽譜ではなく、楽器でもなく、実際に鳴っている音ですらないことを。
グールドは、本当は作曲家になりたかったらしい。演奏家というより「音楽家」という意識だったのではないか。次のグールドの言葉は記憶するに価する。
「自分は、楽譜に書かれ、薄められてしまった音楽ではなく、作曲家のもとに降り立った霊感そのものを音にするのだ。」
作曲家が必ずしも自分の霊感を余すところなく楽譜に書きつけているとは限らないし、楽譜の表現力にも限界がある。音を作り出す楽器にも制約がある。
その制約の中で、「楽譜の向こう側」にあるはずの「作曲家の霊感」、作曲家が本当に表現したかったもの、音として具現化したかったものを、想像力を駆使して探求する。それが、音楽家であるピアニストが行う「演奏」という営みなのだろう。
グレン・グールドのゴルトベルク、もう一度じっくり聴きたくなった。
【関連記事】
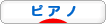
0 件のコメント:
コメントを投稿