
メインディシュは、クラシック音楽やその作曲家についての言いたい放題の対談である。西村朗と吉松隆という同世代の現代作曲家の傾向や性格の違いなんかも垣間見えて面白いのだが、今日は、読みながら考えたことを少し書いてみたい。
なお、例によって(独断と偏見による)読書メモは、こちらの記事にまとめてある。作曲家や作品に関することはこのメモにも入ってないので、そちらに興味のある方は本の方を読んでいただいた方が早いと思う。(悪しからず…)
面白いと思ったのは、吉松さんが紹介している「音楽史の考え方」。その部分を抜き出してみると…。
「バッハは、古い音楽なんじゃなくて若い音楽」そして「現代音楽は、新しい音楽じゃなくて年老いた音楽」なんだって。つまり、クラシック音楽は進化しているのではなくて、18〜19世紀でピークを迎えて衰退しているんだという視点だね。バッハのころが少年時代、ベートーヴェンが青年時代、ワーグナーが壮年時代、そしてシェーンベルクで定年を迎えて、現代音楽でご臨終ということにでもなるかな(笑)。
つまり、音楽は未来に向かっても限りなく進化し続けるという、何となくみんなが思っている?ことの反対の考え方である。
クラシック音楽史を人間の一生と並べてみると、バッハより前の時代に生まれた音楽は、18〜19世紀の働き盛りを過ぎて、定年からもはや「ご臨終」間近というステージに達しているのではないか、ということだ。
これ、何となく説得力を感じてしまう。今、クラシック音楽として一番演奏されているものは、そのピーク時に作られた作品が圧倒的に多い。「クラシック音楽=18〜19世紀の音楽」と言ってもいいほどだ。
そして、「現代の音楽」の行き詰まり感。クラシック音楽は、本当に息絶えようとしているのだろうか? そして、古典芸能になってしまう…。
そうは思いたくないのだが、西村さんの次の発言も合わせて考えると、妙に真実味が増してしまうのだ。
僕は思うんだけど、人間は進化しているんじゃなく劣化していると思う。少なくとも知性の部分では。芸術を鑑賞する鑑賞力とかね。たとえば日本人が100年前に使っていた言葉の半分くらいはもう使ってない。意味も分からない。そうすると、その言葉を使って表現されていたものも言葉が分からないから、どんどん縮小してくる。
まぁ、先のことは分からないし、100年後に現在の音楽(ポップスなども含めて)がどう評価されているかも、本当のところは分からない。じゃあどうするのか? と言っても、なかなか答えは見つからない。
おまけ:音楽が表現しようとしてきたもの、という視点で音楽史を考えてみた(私論・試論)。
バッハのころは宗教音楽。2種類あって、一つは儀式で使うための機会音楽、もう一つは宗教心の表現や神・宇宙の声を現世の音楽に写しとろうとする試み。しかし、スタンスとしてはあくまで職人として。
ベートーヴェンに至って「人間」が主役になってくる、そして精神性が音楽に取り込まれる。喜怒哀楽も。でも、この段階では「人類」であって、個人の感情ではない。理想とか正義とか愛とかが語られる。
ショパンで、音楽が私小説化した。個人的な思いや心情を物語というより詩に乗せて語る、という感じ。
ロマン派はそれに加えて、音楽以外の芸術(絵画・文学)を取り込んだり、光・音・香り・天候などの自然現象を音楽で表現したりした。
ドビュッシーあたりになると、音響自体の美を追求したようにみえる。お手本として自然現象などを参考にはしたが、あくまでも目的は音楽の響き。
ワーグナーあたりで、音楽は興行や演出になり、大規模なオーケストラや奇抜な音響で効果を狙って驚かすようなことが普通になってしまう。大きいことはいいことだ!(私の好みではないが…)
そして「現代音楽」は、新しい何かを創り出すために、既存の枠組み(和声、リズム、メロディ)を破壊することを始めた。そのための多くの「実験」音楽が生まれた。が、破壊のあとには「荒野」だけが残った。その中で、現代の作曲家たちは路頭に迷っている?
…と最後は、勝手な妄想でした…(^^;)。
ここまでのお付合い、感謝! ♪
【関連記事】
《読書メモ『西村朗と吉松隆の クラシック大作曲家診断』》
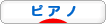
0 件のコメント:
コメントを投稿