
『ラヴェル―回想のピアノ』という本で、著者はマルグリット・ロンという人。
この人は、フランスの女性ピアニストで、ラヴェルと友人で「協奏曲 ト長調」はこの人に献呈されたものとのこと。ドビュッシーやフォーレとも親しく、「ドビュッシーとピアノ曲」「フォーレとピアノ曲」という本も書いているらしい。
さらに、ヴァイオリンのジャック・ティボーとともに「ロン=ティボー国際コンクール」を創設した人である。なんかすごい人の本を選んでしまったなぁ…。
で、内容はまずまず。ほとんどが、ラヴェルの曲についての説明だったりするので、その曲を練習している人や弾いたことのある人にはとてもいい本かも知れない。ただ、聴いて楽しむだけの私にとってはちょっと読みにくい、というのが正直なところである。
ただ、「現代音楽について」という章は、ラヴェル本人がアメリカで行った講演のテキストなので、ここだけは結構面白く読めた。実は、これを読んだ後、少し「現代音楽」に興味が出てきて、シェーンベルクを聴いてみたりしたのである。そのあたりはまた改めて報告したいと思っている。
それから、最後の章、「『自伝的素描』と肖像」がラヴェルの伝記的な内容で、ここは分かりやすくラヴェルを理解するために役に立ったと思う。
結構真面目な人で、自然が好きで子どもが好きで、でもちょっと変わっていて、物忘れが激しくて…。こういう記述もある。「ラヴェルは、非のうちどころなく誠実で信義に厚い人でした。ただ、欺瞞を発見したり、卑劣な行為を認めた時には、怒りは激しいものでした。」
また、自分の曲の解釈や演奏に対してすごいこだわりを持っていて、意図した通りのテンポや強弱とは違う演奏を聴くと機嫌を損ねるような人だったようだ。
例えば、「ボレロ」のテンポに関するくだりは面白かった。思ったより、遅いテンポをイメージしていたようなのだ。現代人が想定するテンポは、ラヴェルに言わせるとかなり速すぎるということに、たぶん、なるのではないだろうか。
まあ、作曲家に限らず、芸術家というのは生み出した作品そのものに語らせる、語ってもらうしかない、と思う。なので、ラヴェル先生の気持ちも分かるが、仕方ないのでは…。
特に、音楽というのは「楽譜」になったとたん、演奏家の解釈と表現力によってしか再現できないので、よりいっそう作曲家のイメージと我々が聴く音楽の間には距離ができてしまうものだと思う。言い換えれば、演奏家の責任が重いということだろう。
ちなみに、ヴラド・ペルルミューテルというピアニストがいて、この人はラヴェルに直接教えを仰いだ人らしい。下記の CD で、「鏡」「水の戯れ」「亡き王女のためのパヴァーヌ」「夜のガスパール」を聴いてみたが、なかなかいい演奏である。ご参考まで。

【関連記事】
《今度こそ生演奏》
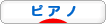
0 件のコメント:
コメントを投稿