
私が、吉松 隆 という名前を知ったのは、昨年、日本人作曲家のピアノ曲(でいいと思うもの)をYouTubeで探していた時である。
なのだが、今回は吉松さんの紹介でもなく、この本の紹介でもない。この本を読みながら、私自身が「現代音楽」からの決別を決めたことを記しておきたい。
この本は、自叙伝としても非常に面白いのだが、彼の作品のとてもよい解説にもなっている。年代順に作品が紹介され、その当時彼自身がどんな音楽に興味を持っていたのか、何を目指していたのか等、本人にしか書けない興味深い内容になっている。
さらに、それと並行して、各時代の音楽状況やそれに対する作曲家の考えなどが綴られていて、現代音楽史のミニ解説としても面白い。
その中で、「現代音楽」への違和感などから紆余曲折を経て、「現代音楽からの決別」(これはこれで作曲家としては大変なことのようだ)が語られるのだが…。その辺は割愛して、私自身の決意?に移りたい。
私自身は、若い頃から何となくクラシック音楽が好きであったが、聴くのは、普通にバッハ、ベートーヴェン、ショパンという感じ。シェーンベルクなどの「現代音楽」で感動した記憶は一度もない。
ただ、同時代の作曲家の音楽には興味があり、それが理解できない(いいと感じられない)ことに「引け目」のようなものを感じていた。
数年前、ピアノを真面目にやり始めた頃に作った《ピアノに関する「興味マップ」》にも、「⑥現代の音楽を知りたい」(現代の作曲家、現代のいいピアノ曲)」という項目を書いている。
でも、《【現代ピアノ曲】日本人作曲家》のように「現代のいいピアノ曲」を探してみても、結局いいと思う曲はどこかに「調性」の感じられる音楽であった。それが私の「感受性」ということだろう。
吉松さんの場合は、感受性に加えて音楽を作る立場としても、音楽にはメロディーやハーモニーは欠かせないという結論に至ったのだと思われる。いくつか、なるほどと思った部分を抜き出してみる。
前衛の時代は「新しけりゃ何でもいいじゃないか」という覇気があったが、その後は向かっている方向がさっぱり分からなくなってしまった。…ここから先…どう「面白く」生きるかは、もはや時代の趨勢などではなく「人それぞれ」になるのだろう。となれば、…音楽は、音楽でなければ、音楽ではないのだ。
メロディやハーモニーをきちんと取り込んだ音楽を現代で作りたい。…それでもなお心の奥のどこかで「現代音楽とのリンク(繋がり)」を信じていた。…
(「鳥の作曲法」とは)現代音楽で使っていた「音列主義(セリエリズム)」や「クラスター」の発想を、「調性」の中で使ってみたら?という発想だ。
音を聴いて人間が…感じる反応は、原始の時代から数万年かけてDNAの奥深く刷り込まれたもの。基本は、心臓(リズム)と呼吸(メロディ)と感覚(ハーモニー)とに連動する本能的なもの…。
とくに、最後の「心臓と呼吸と感覚」というところは、とても説得力があった。人間が聴いて「音楽」と感じるものが「音楽」なのだ。
…ということで、今後は「分からない」音楽に対しては(現代音楽だろうが他の音楽だろうが…)、気にしないことにした。「現代音楽」と呼ばれるものは、すでに役割を終えた「実験音楽」だと思うことにした。
もちろん、新しい解釈(演奏)によって、感動する音楽に蘇る可能性もゼロではないとは思っている。(が、それはそのときのこと…)
そして、「調性回帰」の方向を示した現代の作曲家として紹介されていた、アルヴォ・ペルト(1935〜)、ヘンリク・グレツキ(1933-2010)、スティーヴ・ライヒ(1936〜)などの音楽も、少しずつ聴いてみようと思っている。
【関連記事】
《読書メモ:『作曲は鳥のごとく』(吉松隆)》
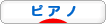

0 件のコメント:
コメントを投稿