
ちょっと期待が大きかったせいか、小説としてはまあまあというところである。ただ、内容には興味があったので読み物としては面白かった。
この本の紹介文にあったように、主に3つの論点を軸に論争が展開される。
- ①東洋人にクラシック音楽が理解できるのか。
- ②美人ピアニストの演奏を、眼を閉じて聴いても感動できるのか。
- ③クラシック音楽とは何なのか。クラシック音楽は最高の芸術なのか。
小説なので、本の内容を紹介するのは遠慮して、上の三つの論点について少し書いてみたい。
まず①。東洋人にクラシック音楽が理解できるか、という点である。演奏家については、音楽として表現できるか、ということになるだろう。
これについては「Yes & No」だと思う。そもそも「音楽を理解する」とはどういうことか、という問題の方が大きいとは思うのだが、それはここでは触れないことにする。
Yesの理由。クラシック音楽自体、すでに世界標準になっていると考えていいのではないか。
その発展過程において、ヨーロッパ以外の音楽や文化の影響を受け、それらを取り込みながら発展してきたわけだから、問い自体が成り立たないとさえ言える。武満徹の音楽がヨーロッパでも評価され、小澤征爾が世界で活躍していることで、それは十分に証明されている。
Noの理由。音楽に限らず、芸術とはその土地や民族の文化の中から生まれるものである。
中世ヨーロッパ音楽は、当時のヨーロッパの宗教を抜きには理解できないし、ショパンの舞曲(ワルツ、マズルカ、ポロネーズ、…)はその踊りそのものと、TPOを知らなければ、本当に理解するのは難しいだろう。
個人的には、念仏と盆踊りのリズムが染み付いた日本人としては、3拍子の舞曲を弾くのは苦手である。
②は、音楽そのものと「ヴィジュアル」または「演奏者」との関係を問いかけているのだと思う。これは微妙な問題である。「Yes or No」、つまり場合による、と思う。
例えば、ユジャ・ワンの場合、私にとっては間違いなく「Yes」である。
しかし、日本での売り出し方(ポスターやCDジャケット)を見ると、たしかに、「ヴィジュアル」に頼っているとしか思えないものも見受けられる。つまり「No」。ただ、この場合、眼を開けていても感動できないと思う。
要は、結局のところ「演奏」または「音楽」そのものが良くなければ、問題外なのではないだろうか。まあ、気楽に楽しむ音楽会やパーティなどでの演奏者は美人である方がいいとは思うが…。
③の前半、「クラシック音楽とは何か」はあまり考えても仕方ないと思う。「人生とは何か」といった問いと同じで、答えはないと思う。もちろん、音楽学(?)上の定義として研究する意味はあるかも知れないが。
後半の「クラシック音楽は最高の芸術か」も、あまり真剣に考える気がしない。好みとか価値観の問題なので、人によって違う、という答えしか思いつかない。
ただ、ヨーロッパ人やクラシック音楽の業界人やクラシック・ファンが、クラシック音楽を愛するあまり、他の音楽を下に見たり、批判するのはどうかと思う。あるとすれば、そういう問題であろう。
と、書いてきて思ったことは、この三つの論点は、ある意味すでに答えが出ている、あるいはそう思っている人が結構多いのではないか、ということ。と考えつつも、こういう本が話題になるということは、本当に納得できてない人も結構いるということ、なのか?
個人的には、これらの論点はさておき、いい(自分がいいと思う)音楽を楽しむことができれば、それで満足である。加えて、自分でももう少し満足できる演奏が出来るようになると、もっといいのだが…。(それはいつの日か?)
【関連記事】
《ユジャ・ワンが小説に?》
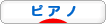
0 件のコメント:
コメントを投稿