Misa's Homepage より抄録
ルネサンス音楽
ウィリアム・バード
バロック音楽
器楽音楽の発展
ジロラモ・フレスコバルディ
アルカンジェロ・コレッリ
ドメニコ・スカルラッティ
バロック期フランスの器楽音楽
フランソワ・クープラン
ジャン・フィリップ・ラモー
ウィリアム・バード
WILLIAM BYRD
(1543-1623)
ウィリアム・バードは、王室礼拝堂の一員として活躍し、《グレート・サーヴィス》などイギリス国教会のための数々の名曲を残しましたが、同時に、最後までカトリックの信仰を守り続けた作曲家でもありました。
バードが3声、4声、5声のためにそれぞれ1曲ずつ作曲したミサ曲は、トマス・タリス(1505?-1585)の《エレミアの哀歌》同様に作曲の意図が謎に包まれた作品です。けれど、抒情的な旋律の流れやデリケートなポリフォニーの線の絡み合い、そして充実したハーモニーの響きが美しい、テューダー王朝時代に作曲された数多くの作品の中でも屈指の名曲と言われています。
カトリック教徒にもある程度まで寛容であったエリザベス1世(在位1558-1603)の庇護があったにしても、バードがその信仰と現実の生活や創作の間の矛盾をどのように受け止めていたかは明らかではありません。けれど、この問題は彼ひとりにとどまらず、この時代のイギリスの芸術家たちが多かれ少なかれ、共通して抱いていた痛みだったようにも思われます。
* * * * *
生前から《音楽の父 Father of Musick》あるいは《ブリタニア(イギリス)音楽の父 Brittanicae Musicas Parens》としてイギリス人の尊敬を集めていたウィリアム・バードの生年は、1622年12月15日付けの遺言書(当時80歳)から1543年と推定されています。エドワード6世とメアリー・テューダーの時代に王室礼拝堂(チャペル・ロイヤル)の音楽家であったトーマス・バードが父であったと考えられていることから、少年時代には王室礼拝堂少年聖歌隊の一員としてトマス・タリスに学んだのではないか、と考えられています。
バードの名前が公式の記録として現れるのは、ロバート・パーソンズ(1530?-1570)の後任として1563年にロンドン北部のリンカンシャーにあるリンカン主教座聖堂オルガニスト兼聖歌隊長として赴任したという記事からです。その後、1570年には再びパーソンズの後任として王室礼拝堂の一員となりました。
1572年には王室礼拝堂のオルガニストとなり、王室礼拝堂での職務をトマス・タリスと分担して行っていました。2人はエリザベス1世の手厚い保護を受け、1572年には21年間に及ぶ楽譜印刷の出版及び販売の独占特許権を与えられ、1585年にタリスが亡くなってからは、文字通りバードの独占権となりました。
このようにエリザベス1世から重用されていたバードですが、1570年代にはロンドンからハーリントンに移り住んでいます。これは、多少ともロンドンから離れた地域の方が“国教忌避者”としてカトリックの信仰を守ることが容易だったためと考えられています。実際、カトリック教徒への弾圧は1580年から次第に強まる傾向を見せ、1585年には国教忌避者のリストにバードの名前があげられるまでになって行きます(それ以前には、彼の妻の名はリストに載っていましたが、バード本人の名は載っていませんでした)。
その後、バードは弾圧を避けるように、カトリック教徒の有力者であったジョン・ピーター卿(1549-1613)の住まいに近い、エセックスのスタンドン・マッシーに移り住み、生涯の最後の30年をその地で送ります。
ピーター卿の周辺には同じ信仰を持つ人々が集まり、秘密の礼拝が行われており、バードもまた、その集会に参加したいたことが当時の記録に残っています。
しかしながら、1619年のアン王女の葬送式には王立礼拝堂の一員として参加しており、1623年6月4日に世を去るまで、チャペル・ロイヤルのジェントルマン(楽員)でもあったのでした。
* * * * *
バードは、カトリック教徒ではありましたが同時にエリザベス1世に重用された王立礼拝堂の楽員でしたから、彼の残した宗教作品の大部分は、ラテン語に寄るものであっても英国国教会のために作曲されていました。また、彼は英語による5曲のサーヴィスと、60曲以上のアンセムを作曲しましたが、彼の残したグレート・ザーヴィスは、イギリス国教会の音楽の中でも、最も優れた作例のひとつに数えられています。
しかしながら、彼の声楽曲の最良のものはラテン語によるミサ曲やモテットだと言われています。
バードの残した最大の傑作とも言われる3声、4声、5声の3曲のラテン語によるミサ曲は、出版時にタイトルページがつけられていなかったためにハッキリとした出版年代がわかっていません。けれど、使われた活字などから《4声のミサ》が1592~93年、《3声のミサ》が1593~94年、最後に《5声のミサ》が1595年頃に出版されたものと推定されています。
バードの3曲のミサ曲は、キリエからアニュス・デイまでの全式文に作曲が行われていることから、イギリスの多声部通作ミサ曲としては特異な作品と言われています。なぜなら、イギリスのミサ曲は13世紀以降、典礼で主として用いられていたソールズベリー教区慣例典礼(Sarum Use)の慣習から、キリエを作曲せずにソールズベリー聖歌を用い、クレドの式文を部分的に削除して短縮するのが原則だったからです。
構成的に言えば、バードの作曲したミサ曲は国教会の典礼音楽の構成に似通っており、エリザベス1世自身がラテン語のミサを好んでいた事から、王室礼拝堂でのミサはラテン語によって執り行われることが多かったと言われます。従って、バードが3つのミサ曲をどのような意図のもとで作曲したかは明らかではありませんが、作品の構造上から言ってイギリス国教会のラテン語によるミサのために作曲された可能性が高いと言われています。
バードは大陸から輸入された通模倣様式(先行する声部の旋律が一定の間隔を置いて他の声部に再現される音楽様式)を完全に使いこなした最初のイギリスの作曲家と言われています。彼のミサ曲は大陸の作品に比べればややホモフォニー的な傾向を感じさせると同時に、華やかさとは縁遠い音楽です。けれど、叙情的で美しい旋律が柔らかく鳴り響き、その作品はイギリス独自のものでありながら、大陸のパレストリーナやビクトリアに勝るとも劣らない作品になっています。
* * * * *
器楽曲について言えば、バードは弦楽器ヴィオールによる小規模な合奏(ヴィオール・コンソート)のためのファンタジアを作曲した初期の作曲家のひとりでもありました。
また、ヴァージナル(チェンバロと同じ機構の鍵盤楽器を、1600年前後、とくにエリザベス1世統治下のイギリスでこう呼びました)のための作品は140曲以上に及び、その作曲の指導的立場にあったと言われています。それらの大部分は変奏形式で作曲され、手書きの曲集「ネヴェル夫人の曲集」(1591)や、「フィッツウィリアム・バージナル曲集」(1612頃~19)などの手書きの選集におさめられています。
また、ヴィオールの合奏(コンソート)の伴奏を持つ独唱、または2重唱の歌曲であるコンソート・ソングの作曲者としても、1588年に出版した曲集《詩篇歌、ソネットおよび歌曲集 Psalmus, Sonets and Songs》において、これらの形式による作品の水準を高める役割を果たしています。
* * * * *
英語による作品よりも、ラテン語によるミサ曲やモテットにより強い表現の意欲を感じさせるウィリアム・バードは、16世紀のカトリック教会音楽の最後の大作曲家と表してもおかしくはないかもしれません。
3つのミサ曲にしても、出版の時期や形態(表紙がつけられていなかった)などから考えて、国教会のラテン語ミサの典礼曲を装ったカトリックの秘密ミサのための曲と考えることもたやすい事のように思えます。
いずれにしても、国教会のイギリスにおいてカトリックの信仰を貫いたバードの緊張感が、その作品や出版形式にかいま見えるような気がします。だからこそ、バードの3曲のミサ曲はルネサンス・イギリスの代表的な作品となり得たのではないでしょうか。
バードの3曲のミサ曲はバードの代表作でありながらも、3曲全部の録音ということになるとあまり多くはないようです。私の持っているのはアルフレッド・デラー指揮のデラー・コンソート盤とピーター・フィリップ指揮のタリス・スコラーズ盤、ポール・ヒリヤー指揮のヒリヤード・アンサンブル盤の3種類です。どれもそれぞれに味があって良い録音ですが、構成やアンサンブルの緻密さという点から言うと、やはりタリス・スコラーズ盤が抜き出ているように感じられます。
「3声のミサ曲」のみですが、タリスの「エレミアの哀歌」とカップリングされているプロ・カンティオーネ・アンティクァの演奏も、滑らかな優しい響きが特徴的で、好きな録音の一つです。
* * *
国教会のための音楽としては、「グレート・ザーヴィス」の録音があります。現在国内版で購入できるのはピーター・フィリップ指揮のタリス・スコラーズ盤だけのような気もしますが、以前EMIで出ていたスティーブン・クレオベリィ指揮のケンブリッジ・キングズカレッジ合唱団による演奏が非常に味のある良い録音だと思います。
* * *
ヴァージナル曲の録音では、ホグウッドの「フィッツウィリアム・ヴァージナル・ブック選集」でバードの作品が8曲取り上げられています。また、バードのヴァージナル曲のみを集めた録音としては、Davitt Moroney による「William Byed / Pavans & Galliards」が非常に面白く聴けました。
ちょっと異色の録音ですが、グレン・グールドがピアノで演奏している「バード&ギボンズ作品集」も注目すべき1枚ではないかと思います。
* * *
コンソート・ソングとヴィオール・コンソートの最新の録音として、カウンター・テナーのジェラール・レーヌとヴィラント・クイケンが主催するアンサンブル・オーランド・ギボンスによる「コンソート・ソング&ヴィオールのための音楽」があります。バードの“出版されなかった”曲を選んで演奏しています。コンソート・ソングとヴィオール・コンソートを交互に演奏するスタイルをとっていて、地味ながらもしっとりとした美しさを醸し出しています。
器楽音楽の発展
basso continuo, trio sonata, concert grosso
バロック音楽が150年間の歴史を通じて持っていた基本的な特色のひとつとして『絶えず動いている低音部』、すなわち通奏低音(バッソ・コンティヌオ basso continuo [伊]、ゲネラル・バスGeneralbass[独])を持つことがあげられます。このため、バロック時代を「通奏低音時代」として定義することがあるほどです。
通奏低音は、一般的に低音の旋律楽器と和音を奏でる楽器の協力によって演奏されます。旋律楽器はチェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、ファゴット、コントラバスなどが担当し、和音楽器としてはチェンバロ、オルガン、リュートなどが一般的でした。例えば、チェロとチェンバロが通奏低音を担当する場合、チェロが伴奏の主旋律を演奏し、チェンバリストは左手でチェロと同じ旋律を演奏し、右手で即興的に和音を付けることになります。
このような通奏低音の土台のに、ひとつ、または複数の上声部(歌の場合も楽器の場合もあります)が自らも装飾音を付加しながら、時には対立し、時には競合する広い意味での協奏形式の音楽が、バロック音楽のもっとも典型的な楽曲でした。
通奏低音は、ルネサンス期後半のヴェネツィア楽派の音楽からその萌芽が見られ、バロック初期にはその形式をほぼ確立しています。
このような通奏低音の発達は、バロック時代に器楽の分野が大きく発達したことを意味しています。つまり、ルネサンス後期からバロック時代にかけて、作曲家は楽器の音色の違いを意識するようになり、それぞれの楽器にふさわしい役割を分担させ、その楽器でなければ演奏できないパートを作り出すようになっていったのでした。
* * * * *
バロック時代は器楽の分野が大きく発達した時代ですが、これは、この時代に楽器がたくさん発明されたという意味ではありません。楽器そのものは音楽の歴史ともに古くから存在していましたし、中世やルネサンス期の絵画や各地の伝統楽器などを見ると、その多様性には目を見張る物があります。けれど、少なくともルネサンス後期になるまで、楽譜の上では、器楽は独立した存在として扱われることがほとんどありませんでした。
そして、ルネサンス後期に入って楽器だけで演奏する曲が増えて来てさえも、初期の作品の多くはオルガンやチェンバロ、リュートといったような、独奏が可能な楽器のための独奏曲であり、声楽の様式を模倣しながらの細々とした試みに過ぎませんでした。それが、バロック時代に近づくにつれて、楽器のパートは声楽とは完全に独立したものとして書かれるようになり、曖昧だった楽器の指定も行われるようになっていきます。
器楽の分野においても声楽同様、その最初の中心地はイタリアでした。ルネサンス後期、ヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂前で行われた式典のために、ジョヴァンニ・ガブリエリらヴェネツィア楽派の作曲家によって書かれたソナタやカンツォーナといった器楽曲は、明らかに楽器の特色や音色などを意識して書かれており、バロック期に発達する協奏様式の先鞭をつけるものとなっています。
ルネサンス期から発達していた鍵盤楽器の分野でも、ソナタ、カンツォーナ、リチェルカーレ、トッカータ、ファンタジア、カプリッチョなどの形式が次第固定されるにつれて、演奏技巧もさらに開拓されていきます。そして、急速な音階の動きや飛躍した音程などの器楽特有の表現方法が追求されるにつれて、音楽の構成もポリフォニー的なものからホモフォニー的なものへと変化していくことになりました。
初期の作曲家としては、アンドレア・ガブリエリ(1510?-1586)、クレウディオ・メールロ(1533-1604)、ジョヴァンニ・マリア・トラバーチ(1575?-1647)らの名前があげられますが、その中でも特筆すべきなのはジラローモ・フレスコバルディ(1583-1643)です。彼は傾向を受け止め、オルガンやチェンバロなどの鍵盤楽器のために優れた作品を多数生みだしました
フレスコバルディは器楽の分野において、モンテヴェルディと同様な先駆的働きをした、イタリア初期バロック時代の最大の作曲家のひとりと評され、。リチェルカーレやトッカータ、カンツォーネなどの音楽形式を駆使して、即興的で自由な作品を数多く生みだしています。
* * * * *
16世紀末から17世紀にかけて、イタリアのクレモナではストラディヴァリやアマーテ、グァルネリといった名工らによって、優秀なヴァイオリンやチェロがつくられるようになります。それに伴って、演奏や作曲法などの面で次々と新しい技法が生み出され、17世紀も後半になると、イタリアの器楽音楽は弦楽器を中心とした合奏音楽の分野の発達が顕著になっていきます。
中期バロック以降のイタリアでは、さまざまな器楽形式が整備され、室内ソナタと教会ソナタの区別があるトリオ・ソナタ trio sonata [伊] や合奏協奏曲 concert grosso コンチェルト・グロッソ [伊] といったバロック期に特有の器楽形式が確立されて行くことになります。
特に17世紀中頃からボローニアを中心に活躍したマウリツィオ・カッツァーティ(1620?~77)、ジョヴァンニ・バティスタ・ヴィターリ(1644?~92)、ジュゼッペ・トレッリ(1658~1709)ら、ボローニャ楽派とも総称される一群の作曲家達による作品は、流麗な旋律と抒情的な表現力を特徴とし、それにふさわしい充実した構成もって組み立てられています。
ボローニャ楽派の作品は、その後の合奏音楽の基礎を作ることになりました。特に合奏協奏曲の形式を整備し、後期バロックにおける協奏曲の発展と完成の基礎を作ったことは、大きな功績と言えるでしょう。
この時代の協奏曲は4楽章以上というのが一般的ですが、トレッリの協奏曲の中には3楽章の、後年のヴィヴァルディの協奏曲を思わせるような作品も存在します。
ローマで活躍したアルカンジェロ・コレッリ(1635~1713)も、その音楽の最初をボローニャで学んでいます。彼は当時、優れた音楽家と認められなければ入会できなかったアカデミア・フィラルモチの正会員に、若干17歳で迎えられたほどの早熟の天才でした。ただし、その主たる活躍の地はローマであり、ボローニャの伝統の枠内に留まってはいませんでしたから、彼をボローニャ楽派に含めることはありません。
コレッリは、トリオ・ソナタと合奏協奏曲という、バロック室内楽の最も基本的な形態の確立と完成とを担った偉大な作曲家でした。彼の音楽は、激情的な表現や技巧の誇示を避けた、独特の気品と格調に満ちたものです。無駄が無く、簡素で均整がとれたやわらかな旋律は、高貴さと、人肌のあたたかさに満ちた優しささえ感じさせてくれます。
* * * * *
コレッリ以後、バロック後期になるとフランチェスコ・ジェミニアーニ(1687-1762)、ピエトロ・ロカテッリ(1695-1764)、フランシスコ・マンフレディーニ(1680?-1748)、ジュゼッペ・タルティーニ(1692-1770)といった作曲家が、それぞれ優れたコンチェルトやソナタを残し、さながらヴァイオリン曲の最盛期の感を呈して来ます。
この時代になると、教会ソナタや室内ソナタ、教会コンチェルトや室内コンチェルトといった区別が曖昧になり、新しい技法や表現法が次々と開拓され、オペラの影響もあって、独奏バイオリンはより技巧的で甘美な旋律を奏でるようになっていきました。
アントン・ヴィヴァルディ(1678-1741)は、バロック後期に最も活躍した音楽家のひとりです。司祭であった彼は、ヴェネツィアの貧民院付属の女子音楽院(ピエタ)の音楽教師をつとめ、400曲以上のソナタやコンチェルト、宗教曲やオペラを残していますが、中でも重要なものは各種の楽器のためのソナタやコンチェルトでしょう。
最初はコレッリの伝統を受け継いだトリオ・ソナタや合奏協奏曲を作曲していましたが、次第にひとつのヴァイオリンを独立させた、俗に「ヴィヴァルディ・タイプ」とも呼ばれるソロ・コンチェルトを主として作曲するようになっていきます。
一般に急-緩-急の3楽章で構成され、速い楽章ではトゥッティ(全合奏)の主題がソロの独奏を挟みながら何度も繰り返され、緩やかな楽章では静かな伴奏を背にソロが朗々と歌い上げるヴィヴァルディのソロ・コンチェルトは、ベートーヴェンやモーツァルトなど、後のウィーン古典派の協奏曲に大きな影響を与えることになりました。
ヴィヴァルディと同じ頃、同じくヴェネツィアで活躍したアレッサンドロ・マルチェッロ(1684-1750)とベネディット・マルチェッロ(1686-1739)のマルチェッロ兄弟やトマゾ・アルビノーニ(1671-1750)も、旋律美に満ちた多くの協奏曲によってヴィヴァルディの向こうを張っています。特に、裕福な家庭に生まれたアルビノーニは自らを「音楽愛好家」を称し、職業音楽家で無いことを誇りにしていました。そのコンチェルトやソナタは、独特の叙情性と気品のあるメランコリーを有しています。
* * * * *
後期バロック時代には、フレスコバルディ以降、一種停滞気味だった鍵盤音楽の分野にもドメニコ・ツィポーリやフランチェスコ・ドゥランテ優秀な作曲家が登場してきます。特に、アレッサンドエロ・スカルラッティの息子のドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)は、スペイン、ポルトガルに長く滞在し、500曲余りのチェンバロのための独奏ソナタを作曲しています。
スカルラッティのチェンバロのためのソナタはすべて1楽章からなっていて、両手の交差やグリッサンドなど、後のピアノ・ソナタにも通じる様々な技法が追求されています。自由奔放とさえ感じられるリズムやメロディーに彩られており、内容的にも後に古典派のソナタを示唆する内容に富んだ、偉大な作品集ということが出来るでしょう。
バロックの完成者と評されるバッハは、フレスコバルディやコレッリ、ヴィヴァルディら、イタリアの作曲家達の器楽作品の主題を自分の作品に借用したり、編曲したりしたことは広く知られた事実です。このことでも明らかなように、バロック期のイタリアの音楽は当時のヨーロッパ音楽の模範となるものでした。
ドイツ、フランス、イギリスなど器楽音楽も、バロック時代はのみならず後の古典派に至るまで、バロック期のイタリアの器楽音楽がなければ存在しなかったと言っても過言ではないでしょう。
バロック時代は、器楽のための音楽がおのれの表現技法を発見し、開拓した時代でした。つまり、近代ヨーロッパ器楽音楽の基礎を作った時代であったと言うことが出来ます。
そして、ヨーロッパの音楽の基礎を担ったのは、声楽においても器楽においても、イタリアの音楽家達だったのでした。
フレスコバルディ、コレッリ、ヴィヴァルディ、ドメニコ・スカルラッティは後で別に取り上げるので、ここではその他の作曲家の録音について触れておきます。
* * *
イタリアの16世紀後半から17世紀の鍵盤音楽の変遷を記録した録音としては、リナルド・アレッサンドリーニが自らプロデュースした、3巻からなる「150 ANNI DI MUSICA ITALIANA(イタリア音楽の150年)」が録音、演奏ともに良いディスクだと思います。必ずしも網羅的な選曲ではありませんが、ことさら身構えたところのない自然体の演奏を楽しむことができます。
クレウディオ・メールロの録音としては、NAXOSで出ているフレドリク・ムニョスが演奏するオルガン・ミサ曲集が、派手さはありませんがまとまった聴きやす作品集になっています。
* * *
ボローニャ楽派の録音も最近はだんだん多くなってきました。トレッリの作品を中心としてボローニャ楽派の4人の作曲家の作品を取り上げた、イヴォール・ボルトン指揮 セント・ジェイムズ・バロック・プレイヤーズによる「ボローニャのバロック音楽」が、快い祝祭的な響きとともに、全体にのんびりした親しみやすさを感じさせる楽しい録音です。
ボローニャ楽派はトレッリが代表格ですが、その作品の中でも《クリスマス・コンチェルト》を含む《合奏協奏曲 Op.8》が有名で、イ・ムジチ合奏団による全曲版はその親しみやすさから言っても、定番の名演と言っていいでしょう。
トレッリの協奏曲としては、Giorgio Sasso 指揮の Rome Instrumental Ensemble による「Symphonies and Concertos Op.5」も非常に良い録音だと思います。
同じボローニャ楽派のヴィターリは《シャコンヌ》が有名ですが、これは作者ははっきりとはしないまでも偽作であることが証明されています。それでも非常にすばらしい作品で、ジーノ・フランチェスカッティやナタン・ミルシテインのモダン・ヴァイオリンの演奏で聴くと至福の一時を得ることができます。
* * *
コレッリ以降のイタリアは、まさにヴァイオリンの時代と言って良いほどで、多くの作曲家たくさんの名曲を残しています。
ジェミニアーニの作品はあまり親しまれてはいませんが、ラ・プティット・バンドやラ・ストラヴァガンツァ・ケルンが演奏する「合奏協奏曲」などを聴くと、その微妙で巧妙な作品技法が新鮮に感じられます。
また、アントニー・プリースとリチャード・ウェッヴのバロック・チェロとクスストファー・ホグウッドのチェンバロによる「6つのチェロ・ソナタ Op.5」もしっかりした輪郭と同時にどこまでも柔らかな陰影のあるチェロの音が非常に印象的な録音です。
ロカテッリの作品としては、《ヴァイオリンの技法》と題された12のヴァイオリン協奏曲からなる協奏曲集がもっとも重要なものでしょう。古くはイ・ムジチ合奏団による演奏もありますが、エリザヴェス・ウォルフィッシュによる全曲録音の「L' Arte del Violino」は本当に素晴らしい録音です。
マンフレディーニの作品としては《クリスマス・コンチェルト》が特に有名です。古い録音ですが、イ・ムジチ合奏団による華やかで艶やかな演奏や、コレギウム・アウレウム合奏団によるおおらかな演奏は非常によい雰囲気を醸し出しています。
最近のオリジナル楽器による録音としては、イル・ジャルディ・アルモニコの演奏による“先鋭的”な録音も、イ・ムジチとは全く違った面白さがあります。
タルティーニというと、《ヴァイオリン・ソナタ ト短調「悪魔のトリル」》が有名です。オイストラフやグリュミオーによるモダン・ヴァイオリンによる演奏はバロック的な様式感はありませんが、圧倒的な存在感で引きつけられてしまいます。
バロック・ヴァイオリンの演奏としては、アンドリュー・マンゼによる「The Devil's Sonata」やロカテッリ・トリオの演奏による「ヴァイオリン・ソナタ集」が良い録音だと思います。また、《悪魔のトリル》は入っていませんが、ファヴィオ・ヴィオンディやリナルド・アレッサンドリーニらによる「Five Sonatas for Violin」は豊かな表現力で傾聴に値します。
* * *
マルチェッロ兄弟は、音楽家としては弟のベネデットの方が優秀であったようですが、映画音楽になった関係で、兄のアレッサンドロの《オーボエ協奏曲》の録音が多く出ています。モダン楽器による演奏ですが、ホリガーとイ・ムジチ合奏団やピエルロとイ・ソリステ・ヴェネティによる演奏はいまだに感動的です。
オリジナル楽器によるアレッサンドロ・マルチェッロの録音としては、サイモン・スタンデジ指揮のコレギウム・ムジク90のよる「'La Cetra' Concertos, Violin Concerto in B flat」も魅力的な演奏を披露しています。
アルビノーニの作品としては、12曲からなる《5声の協奏曲集 Op.9》、その中でも第2番のオーボエ協奏曲が有名です。マルチェッロのオーボエ協奏曲同様、モダン楽器の演奏としてはホリガー/イ・ムジチ合奏団盤とピエルロ/イ・ソリステ・ヴェネティ盤が双璧でしょう。
オリジナル楽器の演奏では、クルストファー・ホグウッド指揮のアカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックが録音したOp.9の全曲録音盤と、サイモン・スタンデジ指揮、コレギウム・ムジク90によるOp.7とOp.9からの選集である「Complete Oboe Concerti」が非常に良い録音だと思います。
* * *
バロック後期のイタリアの鍵盤楽器による作品中の録音は、ドメニコ・スカルラッティ以外はほとんど録音されていないのが現状ですが、セルジオ・ヴァルトロが演奏するツィポーリの作品集「Sonate d'involatura per cimbalo」は非常に素晴らしい録音だと思います。
ジロラモ・フレスコバルディ
Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)
イタリア音楽史上、最大のオルガニストとも評されるジロラモ・フレスコバルディ(1583-1643)は、イタリア初期バロック時代の作曲家の中で、モンテヴェルディと並ぶ重要な人物です。モンテヴェルディが主として声楽のスペシャリストであったのに対して、フレスコバルディは器楽、特にオルガンやチェンバロなどの鍵盤音楽の分野で偉大な業績をおさめました。
* * * * *
1583年にフェラーラで生まれたジロラモ・フレスコバルディは、同地でルッツァスコ・ルッツァスキ(1545-1607)に学びました。1607年にはブリュッセルに旅行しており、この時にヤン・ビーテルスゾーン・スヴェーリンク(1562-1621)に師事したとも言われます。
翌1608年にイタリアに帰国し、当時イタリアのオルガン奏者にとって最高の地位であった、ローマの聖ピエトロ大聖堂のオルガン奏者に就任します。1615年にはマントヴァの宮廷オルガン奏者を、1628~1634年にはフィレンツェの宮廷オルガン奏者を兼ねましたが、その死に至るまで聖ピエトロ大聖堂のオルガン奏者の職を全うしました。
フレスコバルディが聖ピエトロ大聖堂オルガニストへの就任したさいの就任演奏会には、3万人の市民が集まったという有名な逸話も残っています。その数字には多少の誇張があるかもしれませんが、当時、弱冠25歳にして、彼が演奏者としてすでに有名な存在であったことがうかがわれる話です。
また、フレスコバルディは演奏家としてのみならず、教師、作曲家としても後世の鍵盤音楽に大きな影響を及ぼしています。その門下からは、ヨハン・ヤコブ・フローベルガー(1616-1667)をはじめとして、多くの優れたオルガン奏者、作曲家が排出しており、事実上、バロック中期以降の全てのオルガン楽派には直接、間接的に彼の影響が見られると言われています。
J.S.バッハが、フレスコバルディの曲集《フィオリ・ムジカーリ(Fiori musicali)》(1635出版)を通じて、対位法(counterpoint : 複数の旋律を、それぞれの独自性を保ちながら組み合わせる書法)の技巧を学んだのは有名な話です。
* * * * *
彼の作品の大半を占める鍵盤曲は、トッカータやカンツォーナ、ファンタジア、リチェルカーレ、カプリッチョなど様々な形式で書かれていますが、総じて独特の半音階と不協和音の用法やテンポ・ルバート(テンポを柔軟に伸縮させる)の意識的な使用が見られ、表出力に満ちたバロック的な表現を追求しています。
特に、マドリガーレの手法を取り入れた、華麗な妙技を示すかと思うと、次の瞬間には不協和音をならすといったように、小部分が気まぐれに交錯するようにも聴こえるフレスコバルディ独自のトッカータは、厳しいまでの表出意欲と幻想性に満ちています。
フレスコバルディは、独自の霊感を奔放に駆けめぐらせた音楽によって、チェンバロの表現力を高めた作曲家でした。彼自身が《トッカータ集第1巻》(1615年出版)の序文にトッカータの演奏法を述べていますが、そこには
「テンポは拍打ちにとらわれず、演奏者の判断にゆだねられる」
「演奏者は曲の最後まで弾く必要はなく、適当と思われる好きな場所で終わってよい」
などのように、演奏者の即興的な感情の発露を重視する、柔軟で自由闊達とも言えそうな内容が書かれています。
バロック時代までの音楽は、スケッチとしての楽譜をどのように演奏するかは、演奏者の即興性に大きくゆだねられており、そのすべてを楽譜に書き込むことはありませんでした。フレスコバルディの作品も、そのような即興の系譜に位置する作品のひとつだと言うことができるでしょう。
* * * * *
イタリアのオルガン音楽を歴史順に聴いていくと、フレスコバルディのトッカータの静けさに驚かされることがあります。クラウディオ・メルロ(1533-1604)などの先達のヴェネツィア楽派のトッカータが壮麗な名人芸を披露する音楽であるのに対して、フレスコバルディのトッカータはどちらかというと控えめで、瞑想的な独特の雰囲気を感じさせる楽曲に仕上がっているからです。
強靱で無駄のない構成のもと、強弱、硬軟のコントラストを巧みに使用したトッカータは、荘厳と言っても良いような格調の高ささえ感じさせることがあります。後世の音楽家が何時間もかけて表現しようとしたものを、たった数分で表現してしまう霊感にあふれた楽曲が数多く存在しています。
フレスコバルディのトッカータを中心とする鍵盤音楽は、声楽から独立しつつあったイタリア器楽音楽の最初の偉業だと言われています。そしてその流れはイタリアのみならず、フローベルガーらを通して、後のドイツ鍵盤音楽の基礎となっていったのでした。
バロック史上重要な作曲家であるにもかかわらず、フレスコバルディの作品の録音をいざ聴こうと思うと、その少なさに愕然とすることがあります。1983年(生誕400年)と1993年(没後350年)に非常に質の高いアルバムが多数作成されたのですが、その多くは現在では入手が困難であるのが悲しいところです。
フレスコバルディの録音で最初に私が聴いたのは、1970年代に録音されたグスタフ・レオンハルト「チェンバロ・オルガン名曲集」と「カプリッチョ集第1巻」の2枚でした。端正で品位の高い演奏で、特に「カプリッチョ集」の明確さには強い説得力があります。
フレスコバルディの主要な作品の録音の中でも、リナルド・アレッサンドリーニの「フィオリ・ムジカーリ」と「トッカータ集第1巻」は、即興演奏を彷彿とさせるような音楽の自然な流れとセンスの良さで、傑出した演奏だと思います。「トッカータ集第1巻」の方は、日本語解説付きの国内版も発売されていますので、比較的入手が楽なのではないかと思います。
セルジオ・ヴァルトロは、イタリアの Tactus レーベルで「フィオリ・ムジカーリ」「トッカータ集第1巻」「トッカータ集第2巻」「カプリッチョ集」など、フレスコバルディの鍵盤音楽を多数録音しています。いずれも、遅めのテンポで入念に演奏された作品集ですが、そのテンポが生理的に合うか合わないかで、好き嫌いが分かれそうな録音でもあります。
スコット・ロスが死の3ヶ月前に録音したEMI盤も、長く廃盤でしたが2000年になってから Virgin veritas から再発されたようです。絶妙な間合いと自然なテンポでフレスコバルディの魅力を伝えてくれる名録音です。
この他にも、ルネ・サオルジャンの「オルガン作品集」やクリストファー・ホグウッドの「トッカータ集」、トン・コープマンの「オルガン名曲集」など良い録音があるのですが、実質的に入手不可の状態なのは非常に残念なことです。早期の再販、または再プレスを望みたい所です
* * *
フレスコバルディの声楽曲はあまり多くはありませんが、フィレンツェの宮廷オルガン奏者であった1630年に刊行された「アリエ・ムジカーリ」の第1巻と第2巻を演奏したリナルド・アレッサンドリーニ指揮のコンチェルト・イタリアーノの演奏は、モンテヴェルディの初期のマドリガーレとの類似性を感じさせ、一聴に値する録音だと思います。
アルカンジェロ・コレッリ
Arcangelo Corelli
(1653-1713)
バロックと言えば器楽音楽が発達した時代であり、その中でもヴァイオリンを中心としたヴァイオリン族の楽器は、バロック代表する楽器と言うことができるでしょう。特にバロック中期、イタリアでアニトーニオ・ストラディヴァリやニコロ・アマーテといった名工たちが優秀な楽器を作り出した時代は、同時にヴァイオリンのための音楽が新たに作り出されていった時代でもありました。
アルカンジェロ・コレッリ(1653-1713)は、イタリアが生んだ最初のヴァイオリン音楽の巨匠であったと言われます。コレッリの前にも後にもヴァイオリンの名手は存在し、多くの美しい楽曲を生み出しましたが、後世への影響力という点で彼と並ぶものは無いように思われるのです。
* * * * *
イタリア北部ラベンナ近郊のフジニャーで生まれたアルカンジェロ・コレッリ(1653-1713)は、13歳から当時イタリアの音楽教育の拠点のひとつであったボローニャでヴァイオリンを学び、わずか17歳で同地のアカデミア・フィラルモニカに正会員として迎えられました。
このアカデミアへの入会は原則として20歳以上でなければ認められず、10代で特例として入会が認められたのはコレッリと、あとは100年後のモーツァルトのみであったことから考えても、コレッリがいかに若いときから才能を発揮していたかが伺えます。事実、彼はイタリア・バロック中期における、最大の器楽音楽の作曲家に成長していくことになります。
コレッリの名は1675年からローマのサン・ルイージ教会のヴァイオリン奏者のひとりとし記録に現れるようになり、この頃には活動の拠点がすでにローマに移っていたことが伺われます。以後ローマを中心に作曲家、バイオリン奏者として名声を高めて行き、枢機卿ベネデット・パンフィーリや同時期にローマに滞在していたスウェーデンのクリスティーナ女王の後援を受け、コレッリはその活動の初期の段階から安定した生活を送ることができたのでした。
1687年にクリスティーナ女王が亡くなり、1690年にはパンフィーリ枢機卿もボローニャに移ってしまうというように、同じ時期に二人の有力な後援者を失いますが、すぐにパンフィーリ枢機卿の後任である、ピエトロ・オットボーニ枢機卿の元で主席ヴァイオリン奏者兼楽長として仕えるようになりました。オットボーニ枢機卿は芸術家、特に音楽家のパトロンとして有名で、コレッリは彼の厚遇を受け、落ち着いた環境の中で創作活動を続けることになります。
その後、1709年まではコレッリがサン・ルイージ教会の儀式のおりなどに、なんらかの演奏活動を行っていたことが記録からわかっていますす。けれど、1710年のはじめからは公衆の面前にあらわれる事なく、第一線を退いて作品6の合奏協奏曲集の出版作業に取りかかりますが、その出版(1714)を見届けることなく、1713年の1月に60歳でその生涯を終えたのでした。
* * * * *
コレッリは、バロック時代の作曲家には珍しく、その名声に比べると驚くほど作品の数が少ない作曲家です。コレッリ自らが編集して出版された曲集は全部で6つ(作品6は死後に出版)、総曲数で72曲のみであり、自ら出版しなかったけれど楽譜が現存しているという作品を加えても、現代にまで伝わっている曲は80数曲にすぎません。
現存する作品の数が少ないのは、コレッリが遺言で未出版の作品をほとんど破棄させてしまったからだと言われています。けれど、これは同時に、コレッリが自らの作品を厳選し、納得のいくものだけを出版したことをも物語ってます。事実、出版された曲集の完成度は極めて高く、発表当時から高い評価を得ていました。ひとつの作品集が出版されると、すぐに次の作品集が待ち望まれるほどだったと言われています。
コレッリは作品1と3の教会ソナタ集、作品2と4の室内(宮廷)ソナタ集でもって、それまでに様々に試みられていた3声部からなる器楽曲を洗練し、現在トリオ・ソナタとして知られる合奏形態を事実上完成させた音楽家でした。そして、作品5のヴァイオリンのソロ・ソナタ集、作品6の合奏協奏曲集によって、バロック期ヴァイオリン音楽を完成させたと言っても過言でないように思われます。
* * * * *
トリオ・ソナタ、合奏協奏曲、ソロ・ソナタの3分野のいずれにおいても、コレッリの作品はバロック中期の器楽音楽における高い到達点を示し、その発展に偉大な貢献をはたしました。
使われたヴァイオリンの手法は華やかさとは無縁であり、難しいテクニックを避けた、どちらかと言えば表現の幅の狭い作品と言えなくもありません。けれど、旋律と短調の調整の明確さが際立った気品の高い典礼優雅なスタイルは、演奏のしやすさともあいまって、ソナタと合奏協奏曲の普及に大きな足跡を残しています。
このことは、有名な《ラ・フォリア》を含むヴァイオリン・ソナタ集作品5が、18世紀末までにヨーロッパの各都市で40近くの版を重ねるベストセラーとなり、カデンツァの装飾例譜が60種以上も作られたことからもわかるのではないでしょうか。
技巧に走らず奇をてらわない、手堅い構成の作品群であるからこそ、プロの演奏家だけでなく一般の音楽愛好家にも広く迎えられ、時代を超えた普遍性を持ち得たように思われます。
コレッリが完成したトリオ・ソナタも合奏協奏曲も、バロック期の終焉と共に姿を消すことになるのでが、いずれもが諸国の音楽家によって模倣されてゆき、後年、バッハやヘンデルらに継承されて行くことになります。
コレッリの作品は、本当にどれも完成度が高く、甲乙つけがたいところがあるのですが、録音数の多さでは作品5のヴァイオリン・ソナタ集と、作品6の合奏協奏曲集が双璧と言えるでしょう。
* * *
作品5のヴァイオリン・ソナタ集では特に最終12曲目の《ラ・フォリア》が有名で、昔から多くのヴァイオリニストによって演奏されています。モダン・ヴァイオリンによるモノラル演奏ですが、アルチュール・グリュミオーのヴァイオリンにリカルド・カスタニョーネのピアノによる「バロック・ヴァイオリン名曲集」に収められた《ラ・フォリア》は、一度は聴いていただきたいと思います。艶やかなヴァイオリンの響きが美しい魅力的な録音です。
バロック・ヴァイオリンでの演奏と言うことになると、私は寺神戸亮のヴァイオリンによる「バイオリンと通奏低音のためのソナタ集 作品5より」が一番好きです。次いでシギスヴァルト・クイケンの「Sonate a Violino e Violone o Cimbalo, op.V」、Trio Sonnerie (vn.モニカ・ハジェット)の「Violin Sonatas OP.5」、ロカテッリ・トリオ(vn.エリザベス・ウォールフィッシュ)の「Violin Sonatas op 5」ということになりそうです。
《ラ・フォリア》と言えば、フランス・ブリュッヘンによるリコーダー編曲盤も見逃せません。《ラ・フォリア》のみを収めた録音と作品5の全曲盤がありますが、どちらも優れた演奏です。また、有田正広がフラウト・トラベルソで演奏する《ラ・フォリア》も一聴に値すると名演奏だと思います。。
* * *
作品6の合奏協奏曲は全12曲中、第8番が特に有名です。最終章のシチリアーノに『主の降誕の夜のために』という副題がついていて、《クリスマス協奏曲》という題名でこれ一曲だけを収めた録音も数多く出ています。
スタンダードな録音と言うことになると、モダン楽器によるものですが、やはりイ・ムジチ合奏団による演奏は外せないように思います。録音は何種類かあるのですが、アゴスティーニがコンサート・マスターを務めている全曲版の録音が、ややロマンティックではありますが艶やかで明るい弦の音と柔軟性に富んだ表現が魅力的だと思います。
オリジナル楽器での演奏では、シギスヴァルト・クイケンが率いるラ・プティット・バンドの全曲版が、まずはスタンダードな演奏かと思います。多少型にはまりすぎて堅苦しさを感じさせるところもありますが、軽やかな響きが清涼感を感じさせるくれる録音です。もっと伸びやかで軽快な演奏をというのであれば、トレバー・ピノック指揮のイングリッシュ・コンソート盤が良いでしょうか。
エウローパ・ガランティやアカデミア・ビザンティナといったイタリアの演奏家による録音は、いかにも南欧というような明るさときらびやかさが印象的です。時として、やりすぎではないかと思えるようなねっちこさがあって、好き嫌いがきっぱりと分かれそうな演奏ではありますが、イギリスやオランダの演奏家の録音とはまた違った面白さがあります。
* * *
残りの4つのトリオ・ソナタはあまり録音が多くありません。もし全曲を聴きたいのであれば、アカデミア・ビザンティナによる9枚からなるコレッリ作品全集か、分売されているパーセル・カルテットかロンドン・バロックの演奏と言うことになるでしょう。
選集盤としては、トレバー・ピノック指揮イングリッシュ・コンソートのよる「トリオ・ソナタ集」やトン・コープマンやモニカ・ハジェットらが演奏した、非常に歯切れの良い生命感にあふれる「トリオ・ソナタ集」といった、非常に良質の録音が80年代に出されていたのですが、今は入手が難しいかもしれません。
比較的最近録音されたトリオ・ソナタの選集盤としては、エンリコ・ガッティ指揮のアンサンブル・アウロラによる、艶やかで透明感に満ちた演奏があります。
メニコ・スカルラッティ
Domenico Scarlatti
(1685~1757)
バロック時代の音楽一族と言うと、ドイツのバッハ家やフランスのクープラン家などが有名ですが、イタリア、シチリア島のパレルモから出たスカルラッティ家もまた、2代にわたってバロック音楽の歴史を飾る、重要な音楽家を生み出しました。アレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725)はバロック・オペラの大成に大きな影響力を持ち、その息子のドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)は器楽音楽、とくに鍵盤楽器の分野で大きな貢献を果たし、《近代的鍵盤楽器奏法の父》とも呼ばれています。
ただし、ほとんど独力で新しい鍵盤技法を作り出したと思われるドメニコ・スカルラッティは、カルロシュ・セイシェス(1704-1742)やアントニオ・ソレール(1729-1783)といった、何人かのイベリア半島の作曲家以外に後継者を持たず、作品自体もフランスやドイツなどにはほとんど伝わらなかった考えられています。従って、モーツァルトら18世紀の作曲家が、スカルラッティの作品から直接着想を得たという証拠はどこにもありません。
* * * * *
ドメニコ・スカルラッティは、奇しくもJ.S.バッハ、ヘンデルと同じ年である1685年に、ナポリ楽派の重鎮であったアレッサンドロ・スカルラッティの6男としてナポリに生まれました。初期の音楽教育がどのように行われたかは明らかではありませんが、少年時代には父親から教えを受けたと思われます。
1701年、16歳の時には父が楽長を務めるナポリ王室礼拝堂のオルガン奏者兼作曲家となり、1703年にナポリで最初のオペラを発表しています。1705年から、スカルラッティは音楽の修行のためにフィレンツェとヴェネツィアへ赴き、ヴェネツィアでは1708年までの3年間にわたって、フランチェスコ・ガスパーリニ(1668-1727)の元で学んだとも言われますが、確実なことはわかっていません。
この頃、芸術家のパトロンとして有名だったオットボーニ枢機卿の仲立ちで、ヘンデルと鍵盤楽器の技量を競い合ったという逸話が現在に伝わっています。結果は、オルガンの即興演奏ではヘンデルがまさり、チェンバロではスカルラッティの演奏スタイルが好評を得て、雌雄を決することは出来なかのですが、以後はお互いの実力を認め合い、長く友情を結んだと言われています。
1709~14年にかけて、スカルラッティはポーランド王妃マリア・カジミーラに仕え、ローマで王妃の私設劇場のために、毎年新しいオペラを発表しました。1714年に王妃がローマを去った後は、ローマ駐在のポルトガル大使の楽長となります。また、1715年には教皇庁のサン・ピエトロ大聖堂にあるジュリア礼拝堂の学長の地位を得て、宗教曲の分野でも優れた作品を残ました。
サン・ピエトロ大聖堂のジュリア礼拝堂の楽長というポストは、当時のローマ・カトリックの音楽家にとって、宗教音楽の分野では最高の地位だったのですが、スカルラッティは1719年に突然この地位を辞任します。彼が何故そのような行動をとったのか、また辞任直後にどこに滞在していたのかについては現在も不明な点が多いのですが、1719年の終わり頃に、ポルトガルのジョアン5世に仕えるためにリスボンに赴いています。
ポルトガルに到着したスカルラッティは、すぐにポルトガル王家の宮廷楽長として、教会音楽や祝典音楽を作曲するかたわら、王家の子女の音楽教育を行いました。特に王女マリア・バルバラはチェンバロを好み演奏も巧みであったため、スカルラッティはこの頃から王女のためにチェンバロの練習曲を作曲を始めたのではないかと考えられています。
父アレッサンドロが亡くなる前年の1724年に、また、妻を迎えるために1728年に一時イタリアに帰国しますが、1729年にマリア・バルバラがスペイン王子フェルナンド(後のフェルナンド6世)のもとに嫁ぐと、スカルラッティはそれに随伴してマドリードに赴きました。そして、以後1757年に亡くなるまで、王家のチェンバロ教師として終生をスペインで過ごしたのでした。
* * * * *
ドメニコ・スカルラッティの音楽活動は、大きく2つの時期に分けて考えることができます。第1の時期は父アレッサンドロ・スカルラッティが亡くなる1725年、あるいは彼が妻を迎えるために帰国した1728年までとされます。
この時期の彼の作品は、教会音楽やオペラ、室内カンタータが中心で、様式的には父アレッサンドロら当時のナポリ楽派の影響を強く留めており、オペラと宗教音楽の作曲家として活躍しています。
第2の時期は1729年、ドメニコ・スカルラッティがスペインに移り住んだ年に始まるとされています。彼が残した550曲余りのチェンバロ・ソナタは、その大部分がこの時期に書かれたものと推定されています。ただし、それらのソナタは、イタリアで一般的であったトリオ・ソナタでもソロ・ソナタでも無伴奏ソナタでもない、通奏低音の書法からかけ離れた形式で書かれていました。
ドメニコ・スカルラッティの真の創造的な仕事は、スペインでの第2期、そして560曲近く残されたこれらのソナタにこそあったと言って良いでしょう。スカルラッティ自身によってエッセルツィーチ Essercizi(練習曲)と呼ばれていた、これらの1楽章形式のソナタは、1738年に《Essercizi per Gravicembalo チェンバロ練習曲集》として30曲が出版されています。その後、40曲ほどがイギリスで出版されますが、残りの大部分は何冊かの手縞譜として後世に伝わったのでした。
スラルラッティのソナタは、いわゆるウィーン古典派以降の他楽章形式のソナタとは違って、多少の例外はあるものの、ほとんどが単一楽章で単純な二部形式という構成になっています。
しかしながら、提示される2つの主題はしばしば対立する傾向にあり、様々な動機(それ自体がある程度の表現性をそなえた、最小的単位である旋律断片)を組み合わせた、あたかもモザイク模様を見るような旋律の積み重ねは、表現や手法的には古典派前期のソナタのスタイルに近いものだと言えるでしょう。
演奏技法の点では、両手の交差、アルペッジョ(arpeggio 和音の各音を同時ではなく、上または下から順番に演奏する奏法)や装飾音の自由な使用、カスタネットを思わせる同一鍵盤の急速な連打、音程の大きな跳躍などの、当時としては非常に新しいテクニックを演奏に求めています。
* * * * *
ドメニコ・スカルラッティは、1729年に出版した《チェンバロ練習曲集》の序文に「これらの作品のうちに深刻な動機でなく、技術的な工夫をこそ見て欲しい」と記しています。けれどこれは、一種の反語としてとらえるのが妥当ではないかと思われます。なぜなら、スカルラッティのソナタは、確かに構成上の無駄を一切はぶいた極端にシンプルな楽曲ですが、その中に示された楽想の多様性には、目を見張るものがあるからです。
そして、イベリア半島という、強くアラブの影響を受けた土地の音楽、ボレロやファンダンゴ、セギディーリャといった、民族色の濃いスペイン・ポルトガル特有のリズムや旋律の影響を、ソナタのあちらこちらに聴き取る事も可能でしょう。イベリア半島の民族音楽の刺激があったからこそ、スカルラッティは独創的な仕事が出来たと言ってもよ良いのかもしれません。
550曲余りのソナタは、その作品数が膨大であるがゆえに“玉石混淆”の様相を呈しています。けれど「珠玉」という形容が当てはまる作品もまた、数多く存在しているのです。
ドメニコ・スカルラッティが残したソナタは、現在では職業ピアニストにとっては指慣らしやアンコール・ピースとっして、ピアノの初学者にとっては練習曲として使用されています。これは、スカルラッティのソナタの中に、ピアノの演奏に必要な近代的な技法が追求されているからでしょう。後世への影響はどうであったにしろ、《近代的鍵盤楽器奏法の父》とも呼ばれのももっともだと、ソナタを聴くたびに思わせられます。
J.S.バッハの平均律とは全く性格を異にしていますが、それ故にこそ、J.S.バッハと比肩し得るほどの、後期バロック鍵盤音楽の貴重な財産のひとつとなっているのが、ドメニコ・スカルラッティのソナタ集なのです。
スカルラッティのソナタとして伝えられている作品の内、ラルフ・カークパトリック(1911-1984)によって整理されて番号をつけられたものは555曲を数えます。この555曲を全て演奏した録音は、現在の所、若くして亡くなったスコット・ロスによるものだけです。
スコット・ロスによるソナタ集は、まず「全集」であることにその存在意義があるわけですが、それだけに留まらず、智と情のバランスに優れた素晴らしい録音だと思います。揺るぎない技巧に支えられた躍動的なリズム感は、スペイン的な部分は気迫ながらも、スカルラッティが追求した音楽性を充分に表現していると思います。
ソナタの選集盤は、チェンバロ、ピアノ合わせて膨大な録音がありますから、まず、自分の好みの演奏家による録音から聴いてみるのが良いかもしれません。それでも、ピアノによる演奏について言えば、比較対照のためだけでも良いですから、ウラディミール・ホロヴィッツの録音は一度は聴いて欲しいと思います。その音色の素晴らしさは、ピアノによる演奏の中でも出色のものだと思います。
チェンバロによる選集盤では、クリストフ・ルセによる録音が、豊かな音楽性とセンスの良さが際だったています。聴く者に、南欧らしい明るさと躍動感さえ感じさせてくれるような演奏だと思います。
他にも、スコット・ロスの全集からの抜粋盤、グスタフ・レオンハルトの初期の録音、トレヴァー・ピノックによるシャープな演奏も、聴くべき価値があるのではないでしょうか。
珍しいところでは、K番号で分類されていない作品ののみを集めた、曽根麻矢子が演奏する「知られざるソナタ集」も面白い録音です。スカルラッティの作品であると確定できない作品もありますが、多くはスカルラッティの書法で書かれたものであり、何よりも、曽根麻矢子の情熱的で雄弁な演奏は一聴に値します。
ところで、スカルラッティのソナタの分類は、イタリアの研究家アレッサンドロ・ロンゴ(1864-1945)による〈L〉(ロンゴ)番号の分類と、アメリカのチェンバロ奏者・研究家のラルフ・カークパトリックによる〈K〉番号の分類が知られています、現在は、ほぼ年代順に整理されているK番号が一般的に使用されているようです。
* * *
オペラ、宗教曲作家としてのドメニコ・スカルラッティも、最近は徐々に見直しが行われているようです。《ソナタ》に比べれば微々たる物ですが、宗教曲を中心に録音も見かけられるようになりました。
ルネサンス的な典雅な響きの「スターバト・マーテル」は、宗教曲の中でも比較的録音が多い方でしょう。中では、エリク・ファン・ネーヴェル指揮のクレンディ・アンサンブルによる録音が一番完成度が高いのではないかと思います。
室内カンタータのまとまった録音には、 Jean-Christophe Frisch指揮のXVIII-21 Musique des Lumieresによる「Scarlatti: Cantatas」があります。いかにもナポリ楽派らしい、小オペラといった感じの楽曲がセンス良く演奏されています。
Musica Alta Ripaによる「La Famiglia Scarlatti」は、収められている曲の大部分はアレッサンドロ・スカルラッティのトリオ・ソナタと室内カンタータなのですが、ドメニコ・スカルラッティの室内カンタータが1曲と、Francesco Scarlattiというスカルラッティ家の知られざる作曲家の室内カンタータが1曲収録されていて、なかなか面白い録音です。
バロック期フランスの器楽音楽
lute, clavecin, Chambre, concert spirttuel
フランスの器楽音楽を考える時、真っ先に思い浮かべるのはクランソワ・クープラン(1668~1733)やジャン・フィリップ・ラモー(1683~1764)などによるクラヴサン(チェンバロ)曲かもしれません。けれど、ルネサンス後期から初期バロック時代のフランスのサロンにおいて、もっとも持てはやされた楽器はリュートでした。
ルネサンス時代には6コース(6列。1コースは2本一組)が基本であったリュートの弦は、バロック時代に入ると、独奏楽器として広い音域を得るために、最低でも11コース、多くなると13コースという数になりました。そのため、楽器はしだいに大きくなり、音域や表現力も格段に進歩し、独奏楽器として、またはエール・ド・クールの伴奏用として広く使用される事になりました。
当時、王侯貴族達はリュート奏者が奏でる音楽を聴くだけでなく、自らが演奏をすることにも楽しみを見いだしていました。摂政のマリー・ド・メディシス(アンリ4世の妻)はもちろん、ルイ13世も王室のリュート奏者を教師として、その習得に励みました。この頃、王妃アンヌ・ドートリッシュが、エヌモン・ゴーティエ(1575-1651)からリュートを学び始めたと知った宮廷人たちは、こぞって彼から教えを受けようとしますが、その中には宰相リシュリュー枢機卿の姿もあったと言います。
この時期、ジャック・ガロー(1600?-1690?)やシャルル・ムートン(1626-1699?)など、様々な作曲家によってリュートのための曲集が数多く出版されましたが、中でも、宮廷ではなく、もっぱらパリのサロンなどで活躍した、エヌモン・ゴーティエのいとこに当たるドゥニ・ゴーティエ(1603-72)の作品は、その頂点を示すものだと言われています。
しかしながら、このようなリュートの流行は長続きはしませんでした。その理由としては、あまりにも多くなった弦の調弦が難しくなり、保守のために専門家を雇う必要に迫られるなど、素人が趣味として使用するのが難しい楽器になってしまった、という事が第一の理由として考えられています。それに加えて、リュートのあまりにも優雅な音色が、バロックという時代の雰囲気に合わなくなっていったという事も、大きな理由だったかもしれません。
とにもかくにも、あまりに扱いが難しくなったリュートに変わり、サロンでは、より扱いが簡単なクラヴサン(チェンバロ)が好まれるようになりました。そして、17世紀後半に入るとリュートは急速にすたれていきます。けれど、リュートよりも庶民的な楽器と見なされていたギターは生き残り、ルイ14世に仕えたロベール・ド・ヴィゼ(1650?-1725?)らなどによって、作曲が続けられて行くことになったのでした。
とは言え、柔らかな分散和音を特徴とするリュート音楽の演奏スタイルと、同じ調性の舞曲を組み合わせた組曲の形式は、後のクラヴサン音楽に取り入れられて、フランス・クラヴサン音楽の基礎を形作ることになります。
* * * * *
フランス・バロック初期のクラブサン(チェンバロ)音楽は、リュート曲をクラブサン用に書き換えて演奏することからはじまりました。けれど、時代が下がるにつれて、徐々にクラブサンの特徴意識した、独自の作品が作られるようになっていきす。
例えば、ジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエール(1601/02-1672)が作曲した初期のクラブサン曲は、リュートからクラブサンへの移行段階を端的に示しています。装飾音の扱いもリュート的で、クラヴサンではなくてリュートで演奏したとしても、ほとんど違和感が無いかもしれません。
それが、シャンボニエールの弟子だったルイ・クープラン(1626-1661)やジャン・アンリ・ダングルベール(1635-1691)の作品になると、クラブサンの特徴を生かした独自の書法が目立つようになり、舞曲風の組曲でも、2つの異なった旋律を組み合わせる傾向が出てきます。実際、ダングルベールの作品には、ゴーティエのリュート作品の編曲が多く見られますが、リュート曲の装飾方法を利用しつつも、さらに多彩で細やかな音型に変化させていることがわかります。
18世紀に入ると、フランス人のクラヴサンへの愛着はさらに強まることになりました。そして、ルイ・クープランの甥のフランソワ・クープラン(1668-1733)に至って、フランス・クラヴサン音楽はひとつの完成点を迎えます。オルドルと呼ばれる27の組曲にまとめられた、4巻からなるクラヴサン組曲集は、フランスの鍵盤音楽史上、最も重要な作品のひとつとされています。
フランソワ・クープランに次いで重要なクラヴサン音楽の作曲家としては、オペラでも重要な作品を残したジャン・フィリップ・ラモー(1683-1764)があげられるでしょう。ラモーの残したクラヴサン曲は、作品数としてはそれほど多くはありません。けれど、舞曲形式を中心とした、非常に魅力的な小品を残しています。
ところで、バロック期のフランスでは、オルガンのための作品も数多く作曲されました。フランソワ・クープランの2つのオルガン・ミサ曲が特に有名ですが、それ以外にもニコラ・ド・グリニ-(1672-1703)や、ジャン・フランソワ・ダンドリュー(1682-1738)らが、優れたオルガン曲を作曲しています。
フランスのオルガン曲は、クラヴサン曲と同様に、リュート奏法の流れを汲んだ装飾音が特徴的で、自由で色彩的な感覚に満ちています。それらは他国のオルガン音楽にも少なからぬ影響を与えていて、例えば、J.S.バッハはグリニィのオルガン曲集を筆写したり、アンドレア・レーゾン(1650?-1719)のオルガン曲の旋律を、自作の『パッサカリアとフーガ ハ長調 BWV582』の主題旋律として借用したりしています。
* * * * *
フランスの室内楽を考える時、ルイ14世の存在を抜きにしては述べることは難しいでしょう。彼は、その威信をかけて建設したヴェルサイユ宮殿おいて、ルイ14世は、目が覚めてから床につくまでの日常生活のすべてを、儀式がかった手続きにして重々しく行い、その時々には常に音楽を鳴り響かせていたと言います。
ヴェルサイユの音楽家達は、礼拝堂で宗教音楽を担当するシャペル(宮廷礼拝堂楽団)、宮殿内の広間や居間で音楽を演奏するシャンブル(宮廷室内楽団)、狩りなどの野外行事の時に音楽を担当するエキュリ(宮廷野外音楽隊)という、3つのグループに組織されていました。つまり、宮殿内でも室内楽の演奏や作曲は、シャンブルの音楽家達が担当する分野だったわけです。
王侯や限られた廷臣が行き交う広間や居間での演奏には、クラヴサン(チェンバロ)を中心とする、静かで雅な音楽が好まれる傾向がありました。従って、弦楽器ではヴァイオリンよりはヴィオール(ビオラ・ダ・ガンバ)が、木管楽器ではオーボエよりはフルートが愛好される事になり、イタリアではバロック初期に廃れてしまったヴィオールが、フランスではバロック後期まで命脈を保つことになります。
ヴィオール奏者としてルイ14世の寵愛を受け、『天使のように弾く』と言われたマラン・マレ(1656-1728)は、5巻からなる《ヴィオールと通奏低音のための曲集》を作曲しています。また、マレとの対比から『悪魔のように弾く』と称されたアントワーヌ・フォルクレ(1671/72-1745)も、優れたヴィオール曲を残しました。ヴェルサイに仕えた音楽家ではありませんが、マレの師であったサント・コロンブ(?-1691/1701)の残した《2つのヴィオールのための曲集》も、非常に美しい室内楽曲です。
フルートを使用した室内楽曲の作曲家としては、ミシェル・ド・ラ・バール(1675?-1743/44)やジャック・マルタン・オトテール(1674-1763)、ミシェル・ブラヴェ(1700-1768)などの名があげられます。特に、代々エキュリの音楽を担当し、オーボエやフルートなどの木管楽器の改良に力を尽くした、オトテール一族の一員であるジャック・マルタン・オトテールは、近代フルート奏法の基礎を築いた人物として有名です。彼が1707年に著した《フルート、リコーダー、及びオーボエの入門書》は英語やオランダ語にも翻訳され、広くヨーロッパ全土に影響をあたえました。
ところで、バロック期のフランスの室内合奏曲は、オペラでもそうだった様に、イタリアの室内楽を無条件で受け入れたものではありませんでした。そもそも、フランスの音楽家がトリオ・ソナタやソロ・ソナタを作曲しはじめるのは、17世紀末から18世紀初頭になってからで、コレッリがトリオ・ソナタを確立してから20年近くも後のことになります。
例えば、フランソワ・クープランはコレッリのトリオ・ソナタに関心を示し、『コレッリ賛』『リュリ賛』といったトリオ編成の室内合奏曲を作曲していますが、あくまでもイタリア様式とフランス様式の融合を目指しています。イタリアの純音学的な室内楽と比較すると、標題音楽的な性格が強く、華やかさの中にも優雅さや繊細さに重点を置いた、あくまでもフランス的な響きを持った音楽になっています。
* * * * *
ルイ14世の死後、ルイ15世からルイ16世にかけてのフランスでは、すべて文化がヴェルサイユからパリへ、つまり、国王の絶対的な統制から有力貴族やブルジョワ層へと拡散していきました。当然、音楽もその流れの中にあったわけですが、このような時代の流れに拍車をかけたものの一つに、「コンセール・スピリテュア」と呼ばれた公開演奏会の存在ががあります。
コンセール・スピリチュアはルイ14世が亡くなってから10年後の、1725年から王室のエキュリのメンバーであったアンヌ・ダカン・フィリドール(1681-1728)が始めた公開有料演奏会で、オペラなどの公演が禁止された四旬節(キリストの復活に先立つ40日間で、肉断ちと懺悔の期間であり、一切の娯楽を放棄する期間)に開かれていました。
第1回の演奏会は1725年3月28日に開かれ、最初の2年間はラテン語で歌われる宗教声楽作品と、器楽曲を交互に演奏する形がとられましたが、その後、フランス語の世俗声楽曲も取り上げられるようになります。そして、この演奏会は、65年という長期間にわたって開催され、フランス音楽のみならず、イタリアを中心とする外国の音楽を、パリの音楽愛好家が楽しむ場として、オペラを除いた音楽活動の一大中心となっていったのでした。
コンセール・スピリチュアルにはフランス内外を問わず、様々な演奏家が活躍したのですが、その中で特に重要フランス人の演奏家は、1728年にこの演奏会でパリ・デビューを果たしたジャン・マリー・ルクレール(1697-1764)でしょう。
彼はリヨンで生まれたヴァイオリン奏者で作曲家ですが、イタリアのトリノでコレッリに学んだソスミ(1686-1763)に学び、パリに永住後は様々なパトロンに仕えつつ、イタリアのソナタ様式とフランスの様式をバランス良く結合した、ヴァイオリンのための協奏曲やソナタを数多く作曲しました。ルクレールは、フランス・ヴァイオリン楽派の開祖とされています。
* * * * *
ところで、ラモーやルクレールを最後に、フランスは音楽を生産する国から消費する国へと変貌を遂げていきます。バロック時代のフランス音楽は、あくまでもヴェルサイユを中心とした王侯貴族と、一部の裕福なブルジョワ層のものであって、決して一般民衆のものではあり得ませんでした。従って、旧体制(アンシャン・レジーム)の崩壊とともに、フランス・バロック音楽もまた崩壊していく運命にあった、と見るのが正しいのかもしれません。
その後、19世紀に到るまで、パリで活躍をするのはケルビーニやロッシーニ、ショパン、ワグナーなど、主としてフランス以外の国で生まれ育った作曲家でした。
けれど、1871年にサン・サーンス(1835-1921)を中心に「国民音楽協会」が設立され、新しいフランス音楽の設立を目指した時、彼らがフランス的なものの拠り所としたのは、結局はリュリやラモーなどのヴェルサイユ楽派の音楽でした。その研究の成果として、サン・サーンスは、18巻からなる《ラモー全集》を出版しています。
そうして考えて行くと、ヴェルサイユの音楽は民衆から遊離していたにもかかわらず、真にフランス的な音楽だったのだ、と言うことが出来るのかもしれません。ヴェルサイユと民衆を隔てた厚い壁は、同時に、その音楽を熟成させるために必要な時間と空間を、保証するものでもあったのでしょうか。
フランスのバロック音楽の中でも、器楽曲は、最近になって録音が増えてきたジャンルです。その分、あまり知られていない演奏家や曲も多いのですが、我が家にある録音をいくつかあげてみます。フランソワ・クープランとラモーについては別項で扱うのでここには記入しません。
* * *
エヌモン・ゴーティエ Enneond Gaultierは、いとこのドゥニ・ゴーティエ Denis Gaultierとの比較から“老ゴーティエ Vieux Gaultier”とも呼ばれます。私が一番よく聞くエヌモン・ゴーティエの録音はホプキンス・スミスが演奏している「Pieces de Luth du Vieux Gaultier」です。多分、エヌモン・ゴーティエのまとまった作品集としては、唯一のものではないかと思いますが、優美で美しい録音です。
ドゥニ・ゴーティエは、音楽史の本でよく取り上げられているのですが、現在の所、録音はあまり多くありません。ドゥニ・ゴーティエの曲ばかりを集めた、ホプキンス・スミス演奏の「La Rethoriqve Des Dievx」という録音があるのですが、現在は入手するのは難しいようです。
ジャック・ガローやシャルル・ムートンの作品も、ホプキンス・スミス演奏による優れた作品集があります。また、ミヒャエル・シェーファーの演奏による、ガローの作品を含む「バロック・リュート組曲集」も素晴らしい録音です。
ルイ14世のギター奏者だったロベール・ド・ヴィゼの作品は、ギター、リュート、テオルボなどによる様々な録音があります。私が最近よく聴くのは、 ホセ・ミゲル・モレーノがテオルボで演奏している「Pieces De Theorbe」ですが、ホプキンス・スミスがテオルボで演奏した「Pieces de Theorbe」や、佐藤豊彦がギター、リュート、テオルボを駆使した「lute guitar theorbo」など、ヴィゼーについては良い録音がたくさんありますので、色々聴き比べてみるのも楽しいでしょう。
* * *
ジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエールは、かなり多くの作品を残しているようなのですが、残念ながらまとまった録音は無いようです。我が家にあるCDの中では、Davitt Moroneyが演奏している「Livre de Tablature de Clavescin」中に5曲、Edward Parmentierが演奏する「17th Century French Harpsichord Music」の中に3曲が録音されています。
ルイ・クープランのクラヴサン曲全集は、Blandine Verletの演奏によるものと、Davitt Moroney 演奏による2種類があったのですが、現在は入手が難しいようです。最近の録音では、NAXOSから出ているLaurence Cummings演奏の「Harpsichord Suites」と、Globeから出ている Richard Egarr 演奏の「4 Harpsichord Suites for the Sun King」が、手堅い演奏で好感が持てます。
また、近年発見されたルイ・クープランのオルガン曲は、Davitt Moroney の3枚組の全集「Complete Organ Works」で聴くことが出来ます。
ジャン・アンリ・ダングルベールのクラヴサン曲集としては、クリストフ・ルセが2枚組で出した「ダングルベール:クラヴサン作品全集」が、現在では一番入手しやすい録音でしよう。ルセらしい、明確であか抜けた雰囲気を感じさせる演奏です。
スコット・ロスが、チェンバロとオルガンを使い分けている2枚組の「チェンバロとオルガンのための作品集 Pieces pour clavier」も良い録音です。ただし、国内盤は、そろそろ入手が難しいかもしれません。
31歳で夭折したニコラ・ド・グリニーのオルガン曲は、マリー・クレール・アラン演奏の「オルガンによる賛歌(イムヌス)集」と「オルガン・ミサ」という、2種類のすばらしい録音があります。特に「オルガン・ミサ」は、クープランの作品と並ぶほどの傑作として、フランスでは名高い作品です。アランらしい明確な演奏で、国内盤も出ています。
ジャン・フランソワ・ダンドリューのオルガン曲では、Temperaments から出ている「Une Nuit de Noel」に、Martin Gesterの演奏で《12のノエル変奏曲》から6曲が録音されています。また、ダンドリューは3巻からなるクラブサン曲集も残していて、これは ACCORD から出ている Olivier Moumont 演奏の26曲を抜粋した「Pieces de Clavecin」が軽快な演奏を聴かせてくれます。
* * *
マラン・マレの《ヴィオールと通奏低音のための曲集》は、この種の作品としてはかなり録音が多く、良い演奏も沢山あります。何点かをおすすめディスクで紹介していますので、そちらを参照して下さい。
アントワーヌ・フォルクレのヴィオール曲集では、Paolo Pandolfo がヴィオールを担当している「Pieces de viole & continuo, Book 1, suites 1-5 Book」の、情熱的な録音が良いと思います。アントワーヌ・フォルクレの曲をもとに、その息子ジャン=バティストが自作も加えて1747年に出版された、ヴィオール組曲集の完全全曲録音ということで、話題を呼んだ録音でもあります。
サント・コロンブの《2つのバス・ヴィオールのためのコンセール集》は、ジョルディ・サヴァールとヴィーラント・クイケンの2人の大御所が演奏している演奏が一番好きですが、上村かおりとジェローム・アンタイの演奏による「Pieces for two bass viols」も雰囲気のある良い録音だと思います。ヒレ・パールの演奏「Retrouve et Change」は、私の好みからするとやや強めですが、面白く聴ける演奏です。
* * *
ミシェル・ド・ラ・バールのフルート曲は、あまり馴染みがないかもしれませんが、Stephen Preston がフルートを担当している、「Pieces pour la flute traversiere」という、素晴らしい録音があります。
ジャック・マルタン・オトテールの場合は、かなりの数の名録音が存在します。私がよく聴くのは、ブリュッヘンがリコーダーで、バルトルト・クイケンがフラウト・トラヴェルソで演奏をしている「L'Integrale de l'oeuvre pour instruments a vent」や、花岡和生による「プレリュードと組曲」、Jacques Martin Hotteterre による「Ecos Fidelles Preludes. Suites 1-3」などです。その他、NAXOS から出ているフルート作品集もかなり良い録音です。
ミシェル・ブラヴェの作品集としては、花岡和夫と篠原理華がリコーダーとヴォイス・フルートで演奏している「ブラヴェ小品集」と、有田正広がフルートを担当している「ブラヴェ:フルート・ソナタ集」が、まとまった作品集としては一番好きな録音です。特に花岡和夫の録音は、私の愛聴盤のひとつです。
zig zag territoires から出ている「A Deux Fleustes Esgales」は、初期のオトテール・フルートを使った、フルート2重奏ばかりを集めた録音で、ド・ラ・バールやオトテール、ブラヴェなどの作品が収められています。フルートのひなびた音が印象的な、美しい演奏を聴くことが出来ます。
* * *
ジャン・マリー・ルクレールのヴァイオリン曲の録音だと、Fabio Biondi がヴァイオリンを担当している、《ヴァイオリン・ソナタ集 作品1》から4曲を抜粋した「4 sonates du premier livre」、寺神戸亮がヴァイオリンの《ヴァイオリン・ソナタ 作品5》からの抜粋盤「ヴァイオリン・ソナタ集」、Les Talens Lyriques が演奏している《二つのヴァイオリンと通奏低音のための序曲とソナタ集 作品13》「Ouvertures et Sonates en trio」、Simon Standage が主催する Collegium Musicum 90 演奏の《ヴァイオリン協奏曲》作品7と作品10の全曲演奏盤などをよく聴きます。
ルクレールの曲は、モダン楽器でも色々録音があって、グリュミオーの演奏などは独特の雰囲気があって、特に秋の夜などには、ついつい聴きたくなってしまいます。
フランソワ・クープラン
Francois Couperin
(1668~1733)
フランソワ・クープランは、フランス・バロック中期から後期を代表する音楽家のひとりです。彼はその生涯の中で、ヴェルサイユの音楽家として、フランス様式とイタリア様式の融合を試みた室内合奏曲や小規模な宗教曲でも傑作を残していますが、彼の代表作と言えば、やはり鍵盤音楽だと言うことができるでしょう。
オペラやグラン・モテなどの、いわゆる大作の作曲を好まなかったフランソワ・クープランの作品は、どれもが優美で洗練された雰囲気を漂わせ、フランスならではの気品を感じさせてくれます。特に、彼の220曲からなる《クラヴサン曲集》と1716年に出版した『クラブサン奏法 L'art de toucher le clavecin』は、フランス・クラヴサン音楽を完成へと導くものでした。
* * * * *
クープラン家は、16世紀の終わり頃から19世紀中頃にかけて、パリとその周辺で活躍した優れた音楽家の家系でした。代々パリのサン・ジェルヴェ聖堂のオルガニストを務めたことでも知られています。そんなクープラン一族の中で、フランソワ・クープランは最も有名で、同姓同名の叔父と区別するため「大クープラン Couperin le grand」とも呼ばれています。
父親のシャルルはクープランが11歳の時に他界したため、サン・ジェルヴェ聖堂のオルガニストの役割は、彼が18歳の誕生日を迎えるまではドラランドが代行していました。従って、クープラン自身がこの職についたのは1685年からで、その後、1723年にクコラ・クープラン(1680-1748)に譲るまで、サン・ジェルヴェのオルガン奏者として活動を行っています。
1693年に、シャペルの常任オルガン奏者だったトムランが死亡したため、ヴェルサイユで後任のオルガニストを決めるためのコンクールが行われました。このコンクールで、当時25歳だったクープランはルイ14世に見出され、4人のオルガン奏者のひとりとしてヴェルサイユ宮廷に迎えられる事になります。
ヴェルサイユでは、第2のリュリとも呼ばれたドラランドがシャペルやシャンブルの要職を独占していたため、クープラン自身は宮廷での地位にはさほど恵まれませんでした。けれど、病気がちの晩年のルイ14世慰めるため、日曜ごとに宮廷内で行われるコンサートでは、自らの作品をクラヴサンで演奏したといいます。
ルイ14世存命中から、鍵盤楽器奏者、教師、作曲家として宮廷で活躍したクープランですが、彼が正式にシャペルの常任クラヴサン奏者の地位を、ダングルベール(1661-1735)の死後に与えられることが決定したのは、実はルイ14世の死後、ルイ15世が王位に着いた2年後の1717年になってからの事でした。
クープランは、権利の授与が決定した1717年から、シャペルのクラヴサン奏者としての仕事を実質的に開始しますが、健康を害したため、1730年に常任オルガニストの地位ともども、権利を娘のマルグリット・アントワネット・クープランに譲ります。そして、王宮を辞して3年後の1933年9月11日、その生涯をパリの自宅で閉じたのでした。
* * * * *
クープランが1685年から1723年までオルガン奏者を務めた、サン・ジェルヴェ聖堂のために書かれた《2つのミサからなるオルガン曲集 Pieces d'orgues concictantes en deux messes》(1690出版)は、クープラン初期の代表作と言えるでしょう。この曲集には《教区のためのミサ曲 Messe pour les paroisses》と《修道院のためのミサ曲 Messe pour les convents》の二つのオルガン・ミサ曲が収められています。
2曲のうちでも特に《教区のためのミサ曲》は、17世紀フランスのオルガン・ミサ曲の代表曲として知られており、多彩で微妙な音色を追求していった、当時のフランスのオルガン作品の水準の高さを示しています。
ところで、クープランは22歳で発表したこのオルガン曲集以外には、オルガンのための作品を残していません。シャペルのオルガン奏者であった彼は、演奏のみならず、少なからぬ数の作曲を行ったと思われるのですが、それらの作品は書き留められなかったのか、はたまた散逸してしまったのか、その真実は定かではありません。
* * * * *
クープランの作曲したプチ・モテも、彼の作品群の中でも重要な曲種のひとつでした。編成は小さく、合唱の大規模な響きもありませんが、その旋律と歌詞の密接さと描写性の精密さから、この時代のフランスで作曲されたモテットの中でも、特に優れた作品群となっています。
それらのプチ・モテの集大成というべきものが、1715年に出版された《ルソン・ド・テネブレ》です。これは、クープランの宗教音楽の頂点を極めるものであり、その知的で抑制のきいた表現の豊かさと美しさは、シャルパンティエの作品に勝るとも劣りません。フランス・バロック期の宗教曲のなかでも、傑作と呼ばれるもののひとつでしょう。
なお、クープランの現存する《ルソン・ド・テネブレ》は、聖水曜日・聖木曜日・聖金曜日のうちの、最初の聖水曜日のものだけです。《ルソン・ド・テネブレ》や《クラヴサン曲集第2巻》の序文の中で、他の二日分も作曲したことが言及されていますが、それらの楽譜は出版されず、直筆譜なども発見されていないため、どのような曲であったかはわかっていません。
* * * * *
クープランは、器楽合奏曲の分野では、フランス様式とイタリア様式の融合を試みた音楽家のひとりでした。その成果は、傑作として知られる《パルナッス山、またはコレッリ讃 Le Parnasse ou L'Apotheose de Corelli》(1725出版)と、その続編とも言うべき《リュリ讃 Apotheose de Lulli》(1725出版)の二つのトリオ・ソナタに結実しています。
リュリの存命中は、例えばシャルパンティエのように、イタリアの音楽を取り入れたいと思う者がいたとしても、全盛期のルイ14世の権力によって、抑圧される方向にあったわけですが、リュリのあとを継いだドラランドの時代、すなわち17世紀末から18世紀初頭には、イタリアの音楽とフランスの音楽の長所を、意識的に融合しようとする試みが行われるようになりました。
フランソワ・クープランはその先頭に立ち、、フランスにトリオ・ソナタの形式をはじめて導入したと言われています。1724年出版の《趣味の和、または新コンセール集 Les gouts reunis, ou nouveaux concerts》は、フランスで最初に出版されたトリオ・ソナタ集でした。
ところで、各楽章の標題的説明によると、《コレッリ讃》ではコレッリがミューズに導かれてパルナッソス山のアポロの元へいくまでが描かれ、《リュリ讃》ではリュリがパルナッソス山に導かれ、コレッリと共にトリオ・ソナタを奏するという筋書きになっています。フランス趣味とイタリア趣味の結合によって音楽が完成するという考えが、ふんだんに盛り込まれた作品だと言えるでしょう。
その他にも、最晩年の太陽王ルイ14世の沈みがちな気分を慰めるために、1714年から1714年頃に書かれた室内楽曲《王宮のコンセール集 Concerts royaux》(1722出版)や、「フランスの人々」「スペインの人々」「神聖ローマ帝国の人々」「ピエモンテの人々」などの標題が付けられている、組曲《諸国の人々 Les nations》(1726出版)など、注目すべき室内合奏曲があります。
* * * * *
鍵盤音楽家としてのクープランは、鍵盤音楽の詩人であり、音を使った細密画家でもあったように思われます。彼が残した音楽の中でも、全部で4巻からなる《クラブサン曲集》(1713-1730)は、鍵盤音楽史上に燦然と輝く多彩な作品で満ちています。
ルイ14世が亡くなる2年前に出版された《クラヴサン曲集第1巻 Premier livre de clavecin》(1713年出版)では、シャンボニエーニやルイ・クープランなどの先達の影響が色濃く反映され、標題のない舞曲や分散和音に代表されるリュート風の奏法が目立ちますが、1716年に出版された《クラヴサン曲集第2巻 Livre de clavecin》からは、クープラン独自の風刺的な作風が、より明確になっていきます。
各オルドル(組曲)は自然描写や肖像といった共通の性格でくくられたり、対比的な性格の曲を並べて全体の統一がはかられるなど、オルドルごとの性格が明確になり、多くは通して演奏することを想定した構成になっています。
例えば、《第2巻》の最後に収められた第13オルドル《フランスのフォリア、またはドミノ Les Folies francoises ou Les Dominos》の各12曲につけられた標題とその音楽からは、仮面舞踏会の人間模様と、痛ましくも滑稽な『女の一生』とを重ね合わせ、辛辣で風刺的な細密画を描こうとした、クープランの意図が透けて見えるように思われます。
クープランのクラヴサン曲の中には、宮廷の人々、田園で獲物を追う人々、犬の鳴き声や鳥のさえずり、狩猟ラッパ、自然の花や昆虫、教会の鐘など様々なものが登場します。当時の宮廷生活や庶民の生活の雰囲気を、時には愛らしく、あるいやユーモラスに、さらには皮肉や批判を効かせて、クープランは様々に描写していきました。
そして、リュート音楽から連綿と続くこれらの音楽の諸相は、クープランを経て近代フランスのピアノ音楽へと受け継がれ、ドビュッシーやラヴェルなどに影響を与えたのでした。
* * * * *
ところで、18世紀初頭まで、クラヴサンなどの鍵盤楽器を演奏するさいには、親指を使わないのが常識とされていました。クープランは、フランスの音楽家の中で、親指を使う事が有効であると説いた最初の人でした。同じ時期に、ドイツのJ.S.バッハも8本しか使わない事の不合理に気づいていたようです。なお、クープランとバッハとの間で文通などの交流があったとの説もありますが、それを裏付ける証拠は発見されていないようです。
1716年にクープランが著した『クラブサン奏法 L'art de toucher le clavecin』には、上記の親指使用も含めて、運指法や姿勢、演奏者の心構えなどが具体的に著されており、当時の鍵盤楽器奏法の手本としてヨーロッパ全土に広まりました。したがって、クープランの「親指も使う」運指法は、当然ながら、J.S.バッハやヘンデルなど、後世の音楽家の鍵盤楽器のための作品に、多大な影響を与えることにもなったのです。
はじめて購入したクープランの録音が、1981年に国内盤が発売された、グスタフ・レオンハルトが演奏している「クラヴサン名曲集」でしたから、比較的お付き合いは長いはずなのですが、クープランの良さや凄さが実感できるようになってきたのは、ごく最近の事だったりします。
繊細でさりげなくて、うっかりすると淡々と聴き過ごしてしまうのですが、繰り返し聴くうちに、いつのまにか心が捕らえられて離れがたくなる。そんな魅力がクープランの音楽にはあるようです。
* * *
クープランのオルガン・ミサ曲の録音は、クラヴサン曲と比較すると本当に少ないのですが、やはり聖歌も付加してミサの雰囲気を再現したものの方が面白く聴けます。
《教区のためのミサ曲》も《修道院のためのミサ曲》も、『古楽CD100ガイド』(国書刊行会)でも言及されていますが、Jean-Charles Ablitzer がオルガンを担当ている録音は非常に個性的で、特に「Francois Couperin: Messe a l'usage ordinaire des paroisses」は本当におすすめの一枚です。それだけに、現在のところ入手不可能なのが残念でたまりません。
アブリゼル以外でミサを再現した録音というと、マリー・クレール・アランがオルガンを演奏する「教区のためのミサ曲」と「修道院のためのミサ曲」があります。特に、「修道院のためのミサ曲」は最録音されたので、比較的入手がしやすいでしょう。明晰で、細部に注意の行き届いた演奏です。
聖歌は付されていませんが、ジョルジュ・ロベールのオルガン演奏による「小教区のオルガン・ミサ」と「修道院のためのオルガン・ミサ」もよく聴く録音です。手堅い職人芸的な演奏で、アブリゼルやアランのような華やかさこそありませんが、しっとりとした独特な味わいがあって、何かのおりにフッと聴きたくなるような、慕わしさを感じる録音です。
* * *
《聖水曜日のためのルソン・ド・テネブレ》は、やはりジェラール・レーヌ指揮のイル・セミナリヲ・ムジカーレスによる「OFFICE DES TENEBRES」が、とにかく圧倒的な美しさで他を引き離しています。テネブレの前後に配されたグレゴリオ聖歌もすばらしく、特にレーヌの歌唱による第1ルソンの艶やかさは、何とも言えない味わい深さがあります。
レーヌ盤やヤーコプス盤は、独唱者がカウンター・テナーなのですが、クープランの《ルソン・ド・テネブレ》の演奏では、ソプラノ二人が独唱者というのが一般的なようで、現在入手可能な録音でも、伴奏にモダン楽器や古楽器の違いがあったとしても、独唱者がソプラノというものが大部分です。
ソプラノ二人の録音では、エマ・カークビーが独唱者のひとりであるホグウッド盤をよく聴きます。とにかく響きの美しさが際だっていて、聴くたびに心が癒される感じがする録音です。ただ、私はカークビーの声は無条件で好きなので、正常(?)な判断をしているかどうかは定かではありません(笑)。
最近の録音では、クリストフ・ルセが主宰するレ・タラン・リリクと、サンドリーヌ・ピオーとヴェロニク・ジャンスのソプラノ二人による「聖水曜日のための3つのルソン・ド・テネブル」がなかなか良いと思いました。特に第3ルソンの2重唱での、ピオーのやや陰りのある声とジャンスの澄んだ声の絡み合いが、非常に心地よく感じられたディスクです。
クープランのその他のプチ・モテ集としては、クリストフ・ルセ/レ・タラン・リリクのよる「francois Couperin: Motets」の演奏が、私は一番好きです。
* * *
《リュリ讃》と《コレッリ讃》に関しては、ジョルディ・サヴァールとエスペリオンXXによる「Les Apotheoses」の、しっとりとした中に情熱と気品を感じさせる演奏が、とにかくすばらしいです。《諸国の人々》も、やはりサヴァール/エスペリオンXXの演奏がすばらしいです。
クイケン兄弟による「リュリ賛~クープラン:トリオ・ソナタ集」にも《リュリ讃》と《コレッリ讃》が含まれています。標題の朗読も入れるなどの遊び心を持った、輪郭のはっきりした演奏です。少しはっきりしすぎていて、堅さを感じなくもありませんが、面白い録音だと思います。
《王宮のコンセール集》や《新コンセール集》は、クラヴサンのみで演奏された録音も多いのですが、やはり、合奏形式で演奏されたものの方が面白いように思います。
実は、私が一番よく聴くコンセール集は、モダン楽器による抜粋盤です。オーレル・ニコレ(fl)、ハインツ・ホリガー(ob)、ヨゼフ・ウルザーマー(cemb)らが、いかにも合奏を愉しんでいるという感じが良く出ていて、オリジナル性がどうこうと言う余地が無くなってくるほど、圧倒的な存在感がある録音です。
《新コンセール集》に関しては、最近、クリストフ・ルセ指揮のレ・タラン・リリクの、すばらしい2枚組の録音が出ました。柔らかな透明感は、さすがにフランスの演奏団体の強みかと思います。華やかさと繊細さと大胆さが融合した、生き生きとした音楽が全編を通じて流れています。
* * *
クープランの《クラヴサン曲集》に関しては、まず、全集で聴くのか選集で聴くのかという問題があります。出来ればクープランの音楽の変化を楽しむためにも、全集で聴いてみて欲しいところですが、クープランのエッセンスを抽出した選集盤もよいものです。
全集盤の録音というと、古いところではケネス・ギルバート、最近ではクリストフ・ルセとオリビア・ボーモンの録音があります。なかでも、フランス出身のルセとボーモンの録音は、甲乙付けがたいほど優秀な録音だと思います。
あえて言うなら、少しおしゃれで粋な演奏を好む向きにはルセ盤、多少ぼくとつながら、詩情あふれる演奏を好む向きにはボーモン盤でしょうか。ルセ盤には選集もあるので、全集の購入をためらう向きには、ぜひ聴いてみて頂きたいものです。
選集盤では、ルセ盤を除くと、フィリップス社から出たグスタフ・レオンハルトの演奏と、ユゲット・ドレフュスの演奏を、私はよく聴きます。
レオンハルトの演奏は、カッチリとした堅さもあって、必ずしもクープランのクラヴサン曲にむいているとは言い難いところもあるのですが、1995年録音のクープランは、巨匠の風格でもって幽玄の世界を作り出しているように感じられます。
ユゲット・ドレフュスの演奏は、これはもう、貴婦人の気品そのもの、と言った印象があります。演奏方法としては、モダンとオリジナルの折衷と評すべきものなのでしょうが、いかにもフランス的な、暖かさとコケティッシュさが上品に混ざり合った、構成力にすぐれた録音だと思います。
* * *
音楽史の方では触れませんでしたが、クープランは最晩年の1728年に《ヴィオール組曲集 Pieces de violes》を出版しています。2台のヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)と通奏低音のための組曲で、第1番と第2番の2曲がありますが、どちらもフランス・バロック期のヴィオール音楽に、有終の美を飾ざるにふさわしい素晴らしいものです。
録音では、ジョルディ・サヴァールとトン・コープマンの演奏による「Pieces de violes 1728」が、私は一番好きです。
ジャン=フィリップ・ラモー
Jean-Philippe Rameau
(1683~1764)
ジャン=フィリップ・ラモーは、J.S.バッハ(1685-1750)やヘンデル(1685-1759)と同世代の、18世紀フランスにおける最大の作曲家及び音楽理論家です。その作品も音楽理論も、後世に多大な影響を与えました。
ルイ15世(1715-74在位)時代ののロココ趣味を反映したラモーのクラヴサン曲は、ベルリオーズやドビュッシー、ラヴェルなどのロマン派~後期ロマン派のフランスの作曲家に高く評価され、18世紀後半から現在まで、研究や演奏が頻繁に行われて来ました。
けれど、ラモーが最も力を注いだオペラの多くは、リュリやシャルパンティエと同様に、20世紀も後半になってようやく再演されるようになり、やっと、録音でも気軽に聴ける状態になりつつあります。
従って、専門家以外の人間が、ラモーの音楽家としての全体像をつかめるようになったのは、ごく最近の事だと言えるでしょう。実際、ラモーがなぜ偉大なのかを具体的に説明しろと問われた場合、私自身、説明に困る場合が多々あったからです。
* * * * *
ジャン=フィリップ・ラモーは、教会のオルガン奏者をジャン・ラモーを父に、1683年にブルゴーニュ地方のディジョンで生まれました。1701年にイタリアに留学しますが、どうやら短期間でフランスに戻ったらしく、その後はフランス各地で教会オルガン奏者を務めます。
1707年にパリのイエスズ教会のオルガニストになり、《クラブサン曲集第1巻》を出版します。1709年にはディジョンに戻り、父の後を継いでディジョンのノートル・ダム教会のオルガニストに就任しました。クレルモンフェランのオルガニストであった1715~22年に《和声論 Traite de I'harmomie》を執筆、1722年に出版します。
《和声論》が注目を浴び、ラモーはクラブサンと音楽理論を教えながら、パリに定住して活動するようになります。1724年に《クラヴサン曲集》(第2巻)を出版、1732年にはサント・クロア・ド・ラ・ブルトヌリ教会の、1736年にはイエズス会の学校のオルガン奏者に任命されました。
1731年に裕福な音楽愛好家ラ・ププリニエールの私設楽団の音楽監督に就任し、邸宅における音楽の一切をまかされます。ラ・ププリニエールの庇護のおかげで、ラモーは本格的にオペラの作曲に取り組めるようになり、彼が50歳になった1733年に、最初の本格的なオペラ(音楽悲劇)《イポリトとアリシー》が上演されました。
以後、オペラ・バレエ《優雅なインドの国々》(1735)、悲劇《カストールとポリュックス》(1737)、悲劇《ダルダニュス》(1739)など、傑作をつぎつぎと発表し、オペラ作曲家としての名声を確立します。そして、1745年にはルイ15世の宮廷作曲家に任命され、フランス音楽の第一人者としての地位を固めたのでした。
しかしながら、1752年にフランスとイタリアの音楽の優劣をめぐって争われた、いわゆる『ブフォン論争』において、ラモーはJ.J.ルソーら啓蒙主義者によって、伝統的なフランス・オペラの代表者として、攻撃の矢面に立てられます。そして、この論争の前後から、フランス・オペラの中でも、悲劇は次第に上演されなくなっていきます。ラモーでさえも、晩年の13年間にオペラ座で上演された新作悲劇は、《遍歴騎士》(1760)だけという状況でした。
けれど、すでに年金などで収入に困らなくなっていたラモーは、この時期には自ら創作活動から離れて、音楽理論書の執筆の方に力を注いだとも言えるかも知れません。なぜなら、この13年間で、ラモーは23冊もの理論書を発表しているからです。
その後、ラモーは1764年に貴族に列せられたのち、最後のオペラ《アバリス、または最後の北風の神々》の練習中、81歳で世を去りました。そして、彼の葬儀は国葬として執り行われ、その偉業がたたえられたのです。
* * * * *
ラモーの音楽作品としては、クラヴサン(チェンバロ)曲が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。彼のクラブサンを使用した楽曲には、《クラヴサン曲集第1巻》(1706)、《クラヴサン曲集》(1724)、《新クラヴサン曲集》(1728年頃)、《コンセールによるクラヴサン曲集》第1番~第5番(1741)などがあります。
3巻からなる《クラヴサン曲集》に収められた約50曲の小品は、フランソワ・クープランのクラヴサン曲が旋律を重視した、洗練された装飾音のつながりであるのに比べると、旋律よりもハーモニー(和声)を重視した、厚みのある力強い表現を特徴としています。また、鍵盤を駆けめぐるようなダイナミックな音型が好んで用いられ、クープランを「静」とするなら、ラモーは「動」のおもむきがあります。
また、後半の作品になるほど、標題音楽的なものが多くなっていきます。例えば、《新クラヴサン曲集》の第2組曲に収められた『めんどり La Poule』は、ニワトリの鳴き声を描写的に扱った小品です。けれど、それが単なる物まねに終わらず、フランス的な詩情やエスプリを感じさせる、ドビュッシーやラヴェルなどのピアノ曲の先駆けとも言えるものになっています。
《コンセールによるクラヴサン曲集》は、「ヴァイオリンもしくはフルート、ヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)もしくは第2ヴァイオリンとの合奏によるクラヴサン曲集」として1743年に出版されました。けれど、クープランのコンセール集などとは違い、クラヴサンのパートを伴奏(通奏低音)としてではなく、独立した声部としてあつかった、両手とも記譜された最初期の作品のひとつです。
繊細で華やかなロココ芸術らしい楽曲ですが、あくまでも主体はクラヴサンにあって、クラヴサンだけで演奏されても充分に完成された音楽になっています。
* * * * *
1731年にパリの裕福な徴税請負人であったラ・ププリエール家の音楽監督を務めるようになったことは、ラモーの生涯でも重要な出来事でした。ラ・ププリエールの館は、宮廷人や文化人が様々に集まるサロンとして活気があり、優れた音楽家や演奏家が招かれ、音楽会や余興劇が催されていました。従って、ラモーは、優秀な演奏家や新しい楽器を利用してオペラを書くことができたのです。
ラモーはその生涯に30曲ほどのオペラを作曲しましたが、その中でも音楽悲劇《イポリトとアリシー》(1733)、《カストルとポルクス》(1737)、《ダルダニュス》(1739、44改訂)、《ゾロアストル》(1749)、オペラ・バレエ《優雅なインドの国々》(1735)、フランス最初のオペラ・コミックとも言える、喜劇《プラテ》(1745)、1幕物では《ピグマリオン》(1748)などが代表的な作品だと思われます。
ラモーのオペラは、最初作品であるの音楽悲劇《イポリトとアリシー》から、当時規範とされていたリュリの様式を踏まえつつ、イタリア的な斬新な用法を取り入れた、力強いオーケストレーションと劇的な効果の高いハーモニー(和声)を重視した、豊かな表現力に富んでいました。
《イポリトとアリシー》をはじめとして、ラモーのオペラは上演のたびには話題を呼び、ついには、リュリのオペラが上か、ラモーのが上かという、「リュリ派」と「ラモー派」の優劣論争へと発展してゆくことになりました。
* * * * *
ところで、ラモーの晩年におこった『ブフォン論争』のきっかけは、1752年にパリのオペラ座で行われた、イタリアの巡演劇団(ブフォン座)によるペルゴレージのオペラ・ブッファ《奥様になった召使い》の上演でした。
イタリア産のオペラ・ブッファとフランス特有のトラジェディ・リリックの優劣論議は、イタリア音楽擁護派とフランス音楽擁護派の党派論争に発展します。その中で、ラモーは百科全書派を中心としたイタリア音楽擁護派らによって、フランス音楽の象徴として攻撃の矢面に立たされたため、音楽理論家としても受けて立たざるを得ない立場にありました。
2年にわたって行われたこの論争は、簡単にまとめると「イタリア音楽擁護=革新派=旋律至上主義」v.s.「フランス音楽擁護=保守派=和音至上主義」という所に落ち着くように思われます。つまり、当事者達がどのような意図で論争を行っていたにしろ、「旋律(メロディー)」と「和音(ハーモニー)」に優劣をつけようという、かなり無茶な論議を行っていたと言えるでしょう。
ブフォン論争が行われていた間に、ラモーやルソーも含め、様々な知識人によって書かれた、61冊にも及ぶ小冊子がパリ中を飛び交いましたが、当然と言うべきか、明快な答は出ないままに終息していきました。
けれど、保守的だと断じられたフランス・オペラ、中でもトラジェディ・リリックは、啓蒙思想の広がりに伴って昔日の勢いを失い、以後のフランスでは、貴族よりも民衆を対象としたオペラ・バレエやオペラ・コミックが発展していくことになったのでした。
* * * * *
ところで、音楽理論家としてのラモーは、近代和声理論の確立に重要な役割を果たしました。1722年に出版された《和声論》では、18世紀の音響学の発展に基づいて、和声の基本理論を合理的に解明しようとする姿勢が見いだされます。
ヨーロッパ音楽における和声の歴史は、単旋律聖歌に対声部を付け加える試みがなされた中世からはじまり、デュファイらのルネサンス期の音楽家たちは、耳に馴染みやすい3和音(ド-ミ-ソなど)を好んで使いました。けれど、これらに理論的な裏付けを与え、長調と短調の概念などを初めて理論的に論じたのが、ラモーの《和声論》だったのです。
そして、ラモーの《和声論》は、16世紀から行われてきた和声の実践論を体系的に論じただけでなく、1900年頃までのヨーロッパ音楽における、和声の基盤となったのでした。
ラモーは、J.S.バッハやへンデルと並ぶ後期バロックの巨匠でありながら、とりわけオペラに関しては、かなり長い間、不完全な楽譜でしか触れることが出来ないものでした。けれど、ラモー生誕300年記念の1983年から、積極的に復活上演がされるようになって来ています。
特に、マルク・ミンコフスキやジャン=クラウディオ・マルゴワール、エルヴェ・ニケなど、フランス出身の指揮者によるオペラの上演や録音が増えたことは、非常に喜ばしい事だと思います。
* * *
ラモーの《クラヴサン曲集》は、3つの曲集すべてを録音した全曲盤でもCD2~3枚程度なので、出来れば全集盤で聴いて欲しいと思います。ただ、標題音楽的な曲が多い分、へたな演奏だと退屈なだけの音楽になってしまいがちなので、個性がはっきりした演奏者のものを聴いた方が面白いと思います。
代表的な録音をあげると、やはり『古楽CD100ガイド』(国書刊行会)にも書かれている、スコット・ロス盤、クリストフ・ルセ盤、ウィリアム・クリスティ盤の3種類になるでしょうか。
ロス盤は入手しやすい録音ではありませんが、その集中力の高さとバランスが取れた響きの美しさは、他の追随を許しません。絶妙なリズム感による不思議なまでの快さは、酩酊感さえ引き起こします。機会があれば、ぜひ聴いてみて欲しい演奏です。
ルセの演奏は、舞曲的なリズム感を保ちつつも、駆け抜けるようなスピード感に特徴があります。個人的には、もう少しゆったりしている方が、ロココの雰囲気に合っているような気もしますが、爽快感を味わえる面白い録音です。
クリスティの録音は《クラヴサン組曲第1集》は収録されていませんが、1983年の録音とは思えないほどに音質も良く、微妙なテンポの搖れが印象的で、フランス的なエスプリを嫌みなく感じさせてくれます。ロココ的なラモー演奏の基礎となった録音でもあり、歴史的な意味合いからも、一度は聴いて欲しいと思います。
上記3枚には及ばないまでも、1990年以降に録音された《クラヴサン曲集》の中では、個人的にギルバート・ローランド盤、フレデリック・ハース盤、ソフィ・イェーツ盤の3種類が気に入っています。
NAXOS から出ているギルバート・ローランド Gilbert Rowland の演奏は、個性的ではないものの、非常に安定感のある端正な演奏で、誰もが安心して聴ける録音だと思います。
CALLIOPE から出ている フレデリック・ハース Frederick Haas による録音は、装飾音の遊びの部分を良くとらえた、センスの良い演奏を聴くことが出来ます。
CHANDOS から出ている ソフィ・イェーツ Sophie Yates の録音は、クラヴサンの音色を非常に良くとらえた録音です。個人的には、もう少し強さが欲しいような気もしますが、女性的な優しさと清潔感を感じさせる、柔らかで心地よい演奏です。
蛇足ながら、今では滅多に聴かれなくなった録音かもしれませんが、最近古楽を聴き始めたという方は、クラヴサン演奏史をたどる意味からだけでも、一度はロベール・ベイロン=ラクロワのラモーを聴いて欲しい気がします。1955年録音のモノラル盤は無理としても、1970年代のステレオ盤からのCDなら、図書館などにもあるかもしれません。
ラクロワの演奏は、クリスティ以降の現代的な演奏法とはまったく違ったものですが、独特の柔らかな雰囲気があって、充分にフランス・ロココ時代の雰囲気を感じさせてくれる、存在感に満ちた演奏が繰り広げられています。
* * *
《コンセールによるクラヴサン曲集》の録音としては、クラヴサンだけの演奏もありますが、やはり合奏形態になっている物の方が面白いと思います。
代表的な録音としては、やはり、有田千代子(cemb)、若松夏美(vn)、有田正広(trv)、ヴィーラント・クイケン(gamb)による演奏をあげるべきでしょう。細部まで神経が行き届いたアンサンブルが美しい、繊細で趣味の良いディスクです。
フランス・ブリュッヘン(fl)、シギスヴァルト・クイケン(vn)、ヴィーラント・クイケン(gamb)、グスタフ・レオンハルト(cemb)による1971年の録音も、いまだに生き生きとした精気を感じさせる、非常に魅力的な録音です。
1986年に録音された、モニカ・ハジェット(vn)、サラ・カニンガム(gamb)、ミッチ・メイヤーソン(cemb)の3人によるトリオ・ソネリー演奏も、アンサンブルの呼吸が良く、安定感があって聴きやすい録音だと思います。
* * *
ラモーのオペラは、リュリなど比べるとかなり聴きやすいのですが、近世以降のオペラを聴き慣れた耳には、オペラのようには聴こえて来ないのも確かです。従って、初めてフランス・バロック・オペラを聴くという方は、1幕物の《ピグマリオン》から聴いてみるのが良いかも知れません。
《ピグマリオン》の録音では、グスタフ・レオンハルト指揮によるラ・プティット・バンドによる演奏が、スタンダードとして良く取り上げられます。この録音は、レオンハルトの統率力によって細部にまでに神経が行き届き、優美で生命力に満ちています。
ただし、、私の個人的な好みから言うと、Vergin から出ている、エルヴェ・ニケ指揮によるコンセール・スピリチュエル演奏の《ピグマリオン》の、清新なリズム感に満ちた演奏の方が、よりロココ的な雰囲気を伝えているような気がしてなりません。
トラジェデ・リリックの録音では、マルク・ミンコフスキ指揮、ルーヴル宮音楽隊による《ダルダニュス》が、現在入手可能なラモーのオペラの中でも、最高の演奏と録音を誇っています。歌唱、管弦楽ともにすばらしく、ミンコフスキらしいきびきびとした演奏は、名前だけが有名だったこの作品を、最高の形で再現したものだと思います。CD2枚組で、国内版も出ています。
その他のラモーの作品では、まず、ラシーヌの悲劇『フェードル』を下敷きにした、ラモーの最初のオペラ《イポリトとアリシー》に名盤が2枚あります。
マルク・ミンコフスキ指揮、ルーヴル宮音楽隊による録音は、劇的迫力に躍動感に満ちた演奏です。これ対して、ウィリアム・クリステイ指揮、レザール・フロリサンの演奏は、繊細な装飾音の搖れが美しい、アンサンブルの妙を聴くことが出来ます。対照的な録音ですが、どちらも非常に優れた録音なので、あとは好みで選んで頂ければと思います。
オペラ・バレエ《優雅なインドの国々》には、ウィリアム・クリスティ指揮、レザール・フロリサン演奏の全曲盤があります。バレエを見られない状態で、どれぐらいこの曲を理解できるのかは難しい所ですが、クリスティによる管弦楽は、トルコ、ペルー、ペルシャ、北米を舞台にして、エキゾチックな恋物語がくり広げられるこの曲に、とてもふさわしいものだと思います。
その他にも、シギスヴァルト・クイケン指揮/ラ・プティット・バンドによる力強さを感じさせる《ゾロアストロ》、ウィリアム・クリスティー指揮/レザール・フロリサンによる繊細華麗な《カストールとポリュックス》など、魅力的な演奏が多々あります。
* * *
ラモーのオペラの管弦楽組曲盤というのも、いろいろな録音が出ています。ラモーという人は、和声を研究しただけあって、この時代の作曲家の中でも、特にオーケストレーションが巧みなようで、オペラの管弦楽部分だけを抜粋しても、充分に聴きごたえのある1枚物のCDが作れるようです。
どの録音も明快で親しみやすく、オペラを知らなくても純粋に音楽として楽しめる作品に仕上がっていますから、オペラが嫌いだと言う方でも、充分に楽しめる録音だと思います。
特に、フランス・ブリュッヘン指揮、18世紀オーケストラの演奏は、どれも素晴らしいものです。以前フィリップスから出ていた『優雅なインドの国々』や『カストルとポリュクス』の組曲は入手が難しいと思いますが、2002年に GLOOSA から発売された歌劇『ナイス』と『ゾロアストル』の組曲は、まだ入手が可能だと思います。
『イポリトとアリシー』の組曲には、シギスヴァルト・クイケン指揮、ラ・プティット・バンドの名演奏がありました。現在は入手が出来るかどうか難しいところですが、機会があれば、ぜひ聴いてみてください。
【関連記事】
《鍵盤音楽史:バッハ以前》
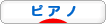
0 件のコメント:
コメントを投稿