1台のスタインウェイ(コンサートグランド)が材木からだんだんと組み立てられ、いくつもの工程を経て出来立ての楽器となり、そこから「スタインウェイ」という名前にふさわしいピアノとして成長していく過程を描いた、まさに「伝記」である。
それは、ハードロック・メイプル(カエデ)の薄板17枚貼り合わせたものを、屈強な男たちがグランドピアノの形に曲げて「リム」を形作るところから始まる。
以前ネットで見た、Christopher Payne という写真家による "Making Steinway" という写真集の写真(↓)を思い出した。
*
この本は、ジェイムズ・バロン(James Barron)というニューヨーク・タイムズの記者が、スタインウェイの工場の職員たちに取材し、ドキュメンタリー風にまとめたものだ。彼は名人級のアマチュア・ピアニストでもあるそうだ。
『スタインウェイができるまで―あるピアノの伝記』
ジェイムズ バロン 著、忠平美幸 訳
青土社、2009年2月

スタインウェイ社の歴史なども織り込んだ、とても興味深い本なのだが、紹介するのは難しい。なので、面白いと思ったことをいくつかトピックス的に書いてみようと思う。
*
ピアノを作る工程一つ一つは、ピアノの仕組みにも興味がある私にとってはとても面白かったのだが、ちょっと感心したのが響板を切り出す工程。
スタインウェイの響板はケースの中にぴったり収まるように作られている。その「ぴったり」の響板を作る方法が、全体的には伝統的な作業の多い工場の中ではちょっと近代的なのだ。
まず「機械がフレームの縁の周囲を滑るように進みながら」形状を「記憶」する。そして、切り出す機械が「『再生』モードで…(記憶した)測定値にしたがって響板を切り整える」ということを行う。昔は、手書きで写し取っていたらしい。
ちなみに、他のメーカーでは少し小さめの響板を使って、ケースとの間にできる隙間にはロープのようなものを埋めたりしているものもあるとのこと。
*
スタインウェイ社はピアノの専業メーカーだと思っていたのだが、初期の頃には防弾チョッキや自動車にも手を出していたことがあると書いてある。
第二次世界大戦中にはピアノを作らせてもらえず、代わりに木製のグライダーを作らされたこともあるらしい。精密な木工技術が生きたわけだ。
ただ、"Steinway & Sons" という名前は、ピアノ以外につけることは考えてなかったようで、バイクやモーターボートや音響機器にも同じブランド名を使っているY社の話がちらっと出たりしている。
でも "Steinway & Sons" という名前のスピーカーとかヘッドホンがあったら、個人的には欲しいかも知れない…(^^)。
*
素晴らしいピアノのための特許をたくさん持っているスタイウェイ社であるが、中にはあまりうまくいかなかったものもあって、ちょっとした問題を起こしたこともある。
それは「テフロン・ブッシング」というもの。
そもそも「ブッシング」とは何か?ということであるが、説明が難しいので、分かりやすかった島村楽器公式ブログの記事を紹介しておく。
✏️ピアノ再生物語第14回
これは、調整がとても難しくて熱や湿気でも「いい感じ」が狂ってしまう。なので、対策として1963年頃からテフロン製に置き換えた「改良」を行ったのだ。
これが、とても評判が悪くて、例えばチャールズ・ローゼンはこんなことを言っている。
「テフロンはカチッカチッという不愉快な音を立てて、みんなをイラつかせた…… 調律師、ピアニスト、あらゆる人をね」
結局、1982年にウール布に戻したが、その布には熱や湿気対策のために、テフロンを含む液体が染み込ませてあるそうだ。
*
この「伝記」の主人公にはいくつかの名前がついている。工場では「K0862」で通っていた。それが出荷されるときに通し番号の「565700」がつけられ、さらにコンサート貸出用のピアノに選ばれると「CD-60」という名前になる。
有名な「ホロヴィッツのピアノ」は「CD-75」という名前だった。
そして、貸出用ピアノ部隊の地下倉庫に置かれた CD-60 はプロのピアニスト15人によって「試弾」され評価される。
エマニュエル・アックスはドビュッシーを弾いたあと「いい感じだ」と言い、ロバート・タウブはショパンを弾き「非常にすばらしい」と言い、スティーヴン・ハフは「まだ未熟で、『履き慣らすのに時間がかかる靴』のようだ」と言い、ラン・ランは「ギアを6速か12速に入れて速く激しく走らせてくれと懇願する車」になぞらえる…。
そういったコメントを参考にしながら、主任調律師のロナルド・コナーズが念入りに調整を進めていく。
*
そして、CD-60 は音楽祭「ザ・ギルモア」でデビューしたあと、様々な音楽祭やコンサートなどで使い込まれ、本来持っていた素晴らしい音を出すようになっていく。
そのあと2年目に、メトロ美術館のグレース・レイニー・ロジャーズ講堂(Metropolitan Museum Grace Rainey Rogers Auditorium)に収まって、この「伝記」は幕を閉じる。
*
おまけ。最初に紹介した "Making Steinway" という写真集のことを思い出したのは、実はこの本を読み終わってからだった。
この写真を見ながら読めば、もっとそれぞれの工程や職人さんたちのことが理解できただろうにと、ちょっと残念な気持ちになった。
もし、この本『スタインウェイができるまで―あるピアノの伝記』
【関連記事】
《ベヒシュタインとはどんなピアノか?》


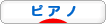
0 件のコメント:
コメントを投稿