これまでの音楽の歴史を一つのものとして捉え、過去の様々な主義や技法を単なる材料として、それらを統合して自分の好きな・聴きたい・弾きたい音楽を創り出す、というのが彼の基本的なスタンスのようだ。
もちろん、そこに至るまでの多様な試行錯誤、統合のための様々な軋轢などを乗り越えながら、北欧の作曲家ラウタヴァーラならではの独自の音楽世界を創り上げたのだと想像する。
彼の音楽を感じ取り理解するのは、残された音楽作品を通してしかありえないとは思うが、ラウタヴァーラ自身の言葉から、その思いを少しは汲み取ることができるのではないかと思う。
主な出典は次の通り。
(Forbes の追悼記事)
(1996年のインタビュー記事)
(The Guardian の追悼記事)
交響曲第5番までは好奇心旺盛な学生?
「若いとき、時代についていくのが重要だと思っていた。だから、モダニストであったし、アヴァン・ギャルドだったし、ダルムシュタット運動にも加わった。セリー音楽も書いた。」
「好奇心は重要だ。…嫌いなことも含めてすべてを試してみること。…学ぶべきことは多く、改善すべきことや進化させるべきことも多い。…私の交響曲がとても異なっている一つの理由はこれだ。」
「交響曲5番までは学生のつもりだった。いろんなことを学んだ。」
例えば、フィンランドの作曲家 Kalevi Aho によると、ラウタヴァーラの交響曲は次のように特徴付けられるそうだ。
第1番(1956年)はポスト・シベリウス、第2番(1957年)は "expressive formalism"(表現的形式主義?)、第3番(1961年)新ロマン主義、第4番(1962年)は完全なセリー音楽、第5番(1985年)は3番と4番が融合したもの。
自分の好きな音楽を書きたい
「しかし、時代についていく限り、時代をリードできないことに気がついた。やりたかったのは、好きな音楽、自分が聴きたい音楽を書くこと。」
「例えば、若いころ12音技術の勉強をし、いくつかの作品を書いた。でもいつも問題に感じたのは、私にとってハーモニーが非常に重要だったこと。だから、50年60年代の前衛作曲家と同じ道を行くことは不可能だった。」
「ピアノ協奏曲第1番(1969年)を書いたのは、自分自身弾きたかったから(自分の技術、自分の手のために書いた)。そして実際にあちこちで弾いた。」
12音技法などは材料、重要なのは組み立て方
「今でも、12音技法は今世紀の音楽家にとってのボキャブラリーだと思っている。問題はそのボキャブラリーをどう構築していくかというシンタックスだ。私のソリューションは、現代的なものと、多かれ少なかれ調性的なハーモニーとの統合を模索すること。」
「12音音楽は学んだが、それは材料にすぎない。問題はそれをどう使うかどう組み立てるか。だからダルムシュタットの作曲家の作品を研究し、実験もしてみたが、自分の好みでないものは作らなかった。私の作品はダルムシュタットのものとは違うものになった。それが私だったのだ。」
本当は、その「シンタックス(統合・構成の方法論)」や「ソリューション(解決法、やり方)」の中身が知りたいと思うのだが、そのあたりはなかなか一言では語れないのかも知れない。
「自分の好み」「それが私(That was me.)」と言うしかないのだろう。今後の音楽学者の研究に期待?…
西洋音楽の長い伝統の一部でありたい
「数千年の西洋音楽の歴史全体を、現代の音楽家は一つの領域として捉えるべきだ。」
「50年代60年代のモダニストたちは『過去の伝統からの決別』を主張するが、私には理解できない。私にとって伝統はとても重要で、私自身もその一部であると考えたい。1940年以降のテクニックだけを使うべきだというのは実に馬鹿げている。」
「当然、多様な異なる(ある人にとっては矛盾・対抗する)システムをつなぎ合わせることは、それぞれのシステムのタブーを破ることにもつながる。しかし、芸術におけるすべてのタブーは近視眼的(時間的・空間的に)であり、しばしば人種的偏見(racism)の証拠だ。」
音楽はもう一つのリアリティー
音楽を言葉で説明することはできない。音楽を説明できるのは音楽だけ。だとすると、音楽とは現実世界とは別の「もう一つのリアリティー」である。
…ということなのかな?次のくだりは…。半分は分かるのだが…。
「(その演奏の)何が違うか、何が足りないかを言葉で言うことはできない。しかし、実際にピアノで弾いてこうだよと言うことはできる。」
「音楽の中にある情報は非常に厳密(exact)なものだ。でも、それは言葉や概念では説明できない。それはもう一つ別のリアリティだ。(我々が生活し感じている?)このリアリティとは異なるものだ。」
「その音楽がハッピーだとか悲しみに満ちているとか、ソナタ形式だとか言うことはできる。だがそれは何も意味しない。音楽に関することを語ることはできても、音楽そのものを語ることはできない。」
北欧の作曲家ラウタヴァーラ?
「シベリウスはとても重要だが、それほど影響を受けているとは思っていない。」
「今ではそうでもないが、50年代には Harald Sæverud(ハラール・セーヴェル:ノルウェーの作曲家)の音楽を熱心に研究したし、非常に好きだった。当時、彼は私がやりたいことに非常に近いことをやっていると思っていた。」
「永遠性が好きだ。宗教的なことも永遠に対する興味から来ていると思う。」
フィンランドの音楽といえば、どうしてもシベリウスの存在を抜きにしては語れない。ラウタヴァーラ自身、シベリウスの推薦でジュリアード音楽院に行ったりもしている。
交響曲第1番は「ポスト・シベリウス」という評価がされることもあるが、本人はどう思っていたのだろう。
また、「ラウタヴァーラの音楽には強いスピリチュアルな要素がある、それは20世紀後半の調性音楽家(Arvo Pärt, Frank Martin, Morten Lauridsen, John Tavener, Pēteris Vasks など)と共通している」という評価も受けている。
これまでいくつかのピアノ作品を聴いた限りでは、やはり彼の音楽の中には北欧的なもの(透明感?)とスピリチュアルな雰囲気を感じざるをえない。
そういったものと「現代音楽」の分厚い響きやとがった打楽器的なリズム感などが、ちょうどよく(私の感性と合うレベルで?)合体しているのではないかと思う。
少なくとも私にとって、ラウタヴァーラの「シンタックス」「ソリューション」は好ましいものであることは確かだ。
【関連記事】

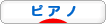
0 件のコメント:
コメントを投稿